
天王寺区逢坂2丁目、うしろに通天閣
逢 坂

天王寺区逢坂2丁目、うしろに通天閣
上町台地へとなだらかにつづく逢坂の道。
恵比須町から逢坂下、合邦辻閻魔堂を経、
逢坂上の一心寺、そして四天王寺に至る。
道に向く逢坂寺の 墓石の
夕つく色を、見てとほるなり

西門はたそがれて 風吹きにけり。
経木書かむ と 言う人あり
夕方四天王寺西門から眺めれば、この坂の下、
さらに大阪湾の方角に太陽が落ちていく。
聖徳太子建立の時代から、
この西方浄土の方位に人々が
手を合わせたことは疑いない。
この国道25号線はさらに河内を経て大和(奈良)へ向かう古代の道でもあった。
古えの道の先には、折口信夫「死者の書」の舞台、二上山、当麻寺がある。
「日想感の内容が分化して、四天王寺専有の風とみなされるやうになつた為、
日想感に最適切な西の海に入る日を拝むことになつたのだが、
依然として、太古のまゝの野山を馳けまはる女性にとっては、
唯東に昇り、西に没する日があるばかりである。
だから日想感に合理化せられる世になれば、此記憶は自ら範囲を拡げて、
男性たちの想像の世界にも、入りこんで来る。さうした処に初めて、
山越し像の画因は成立するのである。」
(山越しの阿弥陀像の画因)
明治32年天王寺中学に入学した折口は、四天王寺の聖霊会で、
のち國學院で、生涯の師と仰ぐことになる三矢重松を目撃する。
四天王寺 春の舞楽の人ごみに
まだうら若き 君を見にけり
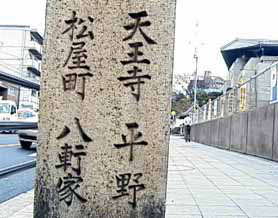
←国道25号線、逢坂2丁目の歩道に建つ石碑。
まっすぐ進むと天王寺、そしてかつて環濠のあった平野郷。
左へ折れると人形、玩具店が並ぶ松屋町(まっちゃまち)、
その先には大川(淀川)の船着場があった八軒家に至る。
江戸時代、そこからは京・伏見へ三十石船が出た。