
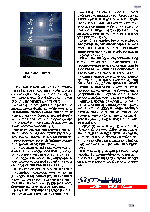
月刊ディオラン 87年3月号 書評
父の本棚
デビュー当時の工藤優作と懇意だった、というと皆一様に驚いた顔をする。LA在住のこの作家を日系人と思いこんでおられる方も少なくはないらしく、一体どこのパーティーで会ったのかとしつこく問われる。なんの事はない、デビュー当時の彼が書いていた雑誌の担当者が私だっただけの事だ。
今でもよく覚えている。当時新宿にあった彼のアパートへ訪ねていって、その蔵書に圧倒された。部屋というよりは本屋の倉庫に近かったろう。古今東西の推理小説・各国の警察関連資料・法医学や犯罪分析学の英文原書がうずだかく積み上げられ、寝るスペースさえなくした彼は、仕事場の事務所のソファで毛布にくるまって寝ていた。あの頃から彼の作品のスケールは国際的で、その物語を支える情報量を見せつけられるたび、あのアパートの本の山を思い出す。
当時の彼の職業は私立探偵。本物の探偵が本物の推理小説を書いていた訳である。小説を地でいく破天荒な作家は数多くいるが、彼ほどの人間はまずもって珍しい。留置所で原稿を書いた逸話や、釈放の身元引き受け人に担当編集者を呼び出した話など、当時の彼に関する話は挙枚に尽きない。
元々がそれだけ話題の多い作家である。世界的な作家として名を知られるようになった現在、彼の消息を伺う者は少なくない。ファンの間には「闇の男爵の集い」といったシャーロキアンまがいの会合さえ開かれていると聞く。人気作家の動向を知らせてくれぬマスコミに業を煮やすファンは多く、パソコン通信などで独自の情報網を巡らせる強者もいるらしい。
古くからのファンならば知っているだろうが、彼が日本のマスコミに登場しないのは理由がある。十数年前の、女優だった奥方との婚約に端を発した騒動が原因だ。行きすぎた報道に業を煮やし、写真誌カメラマン相手の暴行事件を起こしたのだ。幸い刑事訴訟にはならなかったが、以後数年、彼の日本での出版は一切途絶えた。早い話、出版業界を干された訳だ。
以来彼は一貫して海外を市場とした作家活動を行っている。彼の原文は全て英語。日本での出版については翻訳家がつく。そして現在「闇の男爵」シリーズが世界的なベストセラーであることは周知の通り。
その工藤優作の、十数年ぶりの日本語作品が今回の「夏陽炎」である。
主人公は探偵。どこにでもありそうな街の、どこにでもありそうな小さな事件を軸に話は進んでゆく。高校卒業と同時に家を飛び出した娘を探す母、転校生していった小学生時代の親友の消息を尋ねるOL、妻の浮気調査を依頼するサラリーマン…。淡々とした日常を送る登場人物たちのリアリティは同じエンターティメント作家の筆による作品かと疑うほどだ。けれど物語の提示する厄介な謎を前にするとき、この作家の推理小説作家たる真骨頂がかいま見える。
表題作の“夏陽炎”は夫婦間の確執がテーマ。他に中年男の無惨な夢を静謐に描く“澱”子供の残酷を見せつける“あの時きみは…”母と子の愛憎の“タイムアウト”。どの物語も謎が深まる後半から解決にかけて、おそらく途中で本を閉じられるという読者はいないだろう。
犯罪という事象、推理小説という舞台を選びながら、その根底にあるテーマは人間の本質として普遍的な物ばかりだ。おのおのの登場人物の重厚な描写は、その人物の出生から物語時点までの人生を語り、そして犯罪に至るまでの感情の起伏が、謎が解かれる息詰まるような緊迫感と共に読者に迫ってくる。
人の業を見せつける物語に救いをもたらすのは、主人公の探偵だ。人当たりよく、時に饒舌でさえありながら、決して周囲の誰にも心を許さない。女達の熱い視線を向けられ、恋の機微に戯れながらも、最後は寡黙に全てを拒絶する。懐に抜き身の刀を呑んでいるような、凄絶なほどの感情を見せながらも、奇妙な透明感を感じさせる。この男に解かれるからこそ、全ての物語の負の感情は慈しむべき物として読者に見いだされる。
代表作である「闇の男爵」シリーズが優れたエンターティメント小説であると同時に優れた推理小説である事は、誰もが知っていることだ。この「夏陽炎」は、ある意味「闇の男爵」とは対極にある作品かもしれない。推理小説というエンターティメント色の濃い物語でありながら、一種純文学以上に深く濃く描き込まれた人物たち。その織りなす物語は、あまりにも鮮烈であまりに哀しい。
この作者の一貫したテーマは今も昔も変わっていない。曰く「かっこいい男を書く」――どんな難事件も解決してしまう名探偵こそ、細分化した知識を統合して複雑化た時代の謎を解くヒーローなのだと言う。その単純きわまりない動機がエンターティメントとしての核だとしたら、これほどまでに完成度の高い物語となるための牽引力は、彼の知識欲・行動力・観察眼だろうか。
蔵書にアパートを追い出され、依頼に体を張っていたあの頃の彼の中に、すでにこの物語の萌芽はあったのかも知れない。日本を飛び出し、世界を市場と見定めた作家の久しぶりの贈り物として、物の判る大人の男にぜひ読んでいただきたい作品である。