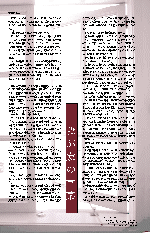
月刊家庭生活 91年7月号 特集・帰国子女
我が家の言葉
家族について書いてくれという依頼は少なくないが、私はそれを引き受けることはめったにない。彼らのプライバシーを守るためでもあるが、本当の理由は別にある。
自慢できるような話が一つもないのだ。
何しろ月に一度は必ず何かで妻と言い争う(大抵詫びを入れるのは私の方だ)。一人息子は推理小説マニアでいささか変わり者だ。パーティージョークのネタには事欠かないが、胸を張って他人様にお聞かせできるような格好良い話題が全くない。記憶のドブをさらってみても、浮かんでくるのは恥ずかしい話ばかりである。
ところが最近、思いもよらなかった事実が判明した。問題児だとばかり思っていた息子が、優等生だと言うのである。親バカな話で恐縮だが、とりあえず自慢したい一心でこの依頼をお受けした。結婚して10年、初めてできる自慢話である。見苦しいとお思いの向きもあろうが、聞いていただきたい。
学生時代の私は、人並み外れた問題児だった。小学生で隣の組の女の子と隣町まで駆け落ちしたのを皮切りに、授業の内容を巡って先生と言い争うわ、上級生をたたきのめすわ…。一度など二階の教室の窓から飛び降りて授業をエスケープし、担任の女性教師を失神させたほどである――その時は警察まで呼ばれて大変な騒ぎになった――。だから自分の息子も間違いなく問題児だと、信じて疑っていなかった。
もちろん、理由は他にもある。
息子は生まれてから小学校に上がるまでの年を、イギリスで過ごした。これは私の仕事の事情で、当時私の作品を評価してくれる出版社があちらにしかなかったのである。だから息子は生まれも育ちもイギリスであり、生活は当然全て英語。日本語は家族である私たちと話す時しか使っていなかった。
そんな彼を日本の学校に入れたのは、親のエゴだったと言えなくもない。
どんなにイギリス生まれのイギリス育ちでも、“イエロー”であり“ジャップ”である事実は変わらない。ならばそうである事に誇りの持てるよう、日本人としての自覚を持たせるのが親の義務だと思った。親の外国かぶれが原因で中途半端なアイデンティティしか得られなかった子供達を、私も妻もあの国でたくさん見ていた。そんな不幸を、息子に背負わせたくなかったのだ。
かくして私たち夫婦は「息子が何をしでかしても決して驚くまい」の覚悟とともに息子を日本に連れてきた。
最初こそ戸惑った物の、息子はすんなり日本の学校に馴染んでくれたようだった。登校拒否も覚悟していた私たちにとっては、それだけでも御の字に思えたものである。今思い出せば、当時は息子の発する質問に夫婦二人でへどもどしていた。「どうしてみんな髪の毛が黒いの?」「どうしてみんな同じ顔なの?」「どうしてみんな考えもしないで“はい”って返事するの?」…子供の目の素直さと残酷さを痛感したものである。
そのうちに、息子が奇妙な行動を始めた。
当時から私の元には、イギリスの友人が毎月のようにあちらで出版されたミステリーの新刊が届いていた。500ページ以上もあるようなハードカバーの原書、あるいはペーパーバック、それに資料として取り寄せた公文書など…。もちろん一般向けの文章であり、とても小学生の読める内容ではない。
その本を手に私の書斎にやってきた息子は「読んでくれ」とせがむようになった。
二時間でも三時間でも私の膝に座り込んだまま、息子は私が読むのを聞いていた。私が仕事で忙しいときは妻の所へ行って、同じ事を頼んだ。殺人が起きたり強盗が入ったりする小説である。果たしてこんな内容が面白いのだろうかと疑問に思ったものだが、息子に飽きた様子はない。むしろ貪るように文字を追っていた。そうして私に聞くのだ。「メアシャム(海泡石)ってなあに?」「この部屋に窓は2つだけなの?」「この人は左利きなの?」質問は、全て英語だった。
息子を交えた家族会議が開かれて、ルールが決められた。特に断りがない場合、我が家の公用語を英語とすること。相手が日本語で話しかけた時は日本語で返すこと。お客様には日本語で挨拶すること。――早い話、イギリスで暮らしていた頃と、家の内と外で使う言葉が逆になった訳である。
イギリスで生まれてイギリスで育った息子にとって、あの国は日本以上に祖国なのだろう。その祖国と“言葉”を通じて結びつこうとした所で何の不思議もない事だ。月に一度送られてくる本は、息子にとって祖国からの便りにも思えたろう。だから手に余すような分厚い本を読んでくれとせがんだし、意味が判らなければ質問もした。
彼が真剣に求めているものを、私たちは与えるべきだと思った。
その後3年間ほど、息子は本を持って私の膝に座るのをやめなかったが、時間は30分ほどに短縮された。今ではどうやら息子の知識が本の内容に追いついたらしく、勝手に書庫で自分の気に入った本を読んでいる。無論殺人や強盗の小説である。
――私が自分の息子を問題児と信じて疑わなかった理由をお判りいただけたろうか。家の中の会話をすべて英語で通し、家に友達を連れてきた事もない(家の庭で女の子と遊んでいるのを見たことはある。何か間違いを起こしはしないかと妻は本気で心配していた)。ヒマさえあれば埃臭い書庫に入り浸り、推理小説を読んでいる…。その息子が優等生であるなどと、誰が想像できるだろう。
担任の先生の言によれば、総じて息子の成績は優秀らしい。むら気でも短気でもなく、授業中は大人しい(これが私には信じられない!)。口べたで頑固な所はあるが、話して納得させれば素直にいうことを聞く。女の子や下級生に対しては、ぶっきらぼうだが紳士的であること。他人の争いごとには無関心だが、弱い者いじめや卑怯な争いには仲裁に入ること。
子供というのは、親の想像のはるかに上をいくものらしい。私も妻も、その話を聞かされてしばらくは呆然としていた。喜んでいいのか疑ってかかるべきなのか…。
ともあれ、英語と日本語の間を行き来して、息子は自分の行動基準を定めてきたようだ。日本人にも英国人にも通じる人としての基準を持ってくれたというのなら、親としてこんな嬉しい事はない。訪ねてくる編集者に変人扱いされながら、セールスマンに逃げ出されながら守ってきた我が家のルールが、大きな実を結んだのだから…。