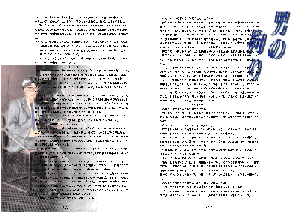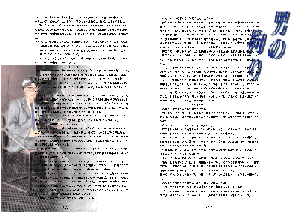
月刊MEN'SFASHION 97年8月号 連載インタビュー
「いえ、マスコミ嫌いという訳ではないんですが」
待ち合わせの時間きっかりに約束のバーに現れた工藤氏は、かねて用意の質問にいくらか困ったような顔をした。肩をすくめる仕草がいかにも外人めいていて、何となくはぐらかされてしまう。後から聞いてみたら、一生の1/3近くを海外で暮らしているとの事だった。
工藤優作。女流ミステリー作家が気炎を上げる今日の文壇ににおいて、時流に流される事なく独自の位置を守り、なおかつ他から頭一つ抜きん出た観のある作家である。ロサンゼルスを拠点に世界各国を飛び回り、刻々変化する世界とその犯罪を見守る中で生まれるその作品は、古典的推理小説と社会派ミステリーの幸福な融合でもある。
著書が広く世間に知られている割に、氏自体がマスコミに登場する機会はあまりに少ない。
「作品のためにこちらから取材をさせていただくのに忙しくて、お受けする時間がないんです。…それに結婚した時に一生分、そういう事は済ませてしまったかな、という気もしてますし」
いくらか苦笑を含みながらそう言われれば、少なくとも日本のマスコミはそれ以上の言葉を持てないだろう。もう20年近く前、人気の絶頂だった当世一の美人女優を、ほとんど駆け落ち同然に引っさらっていった氏の結婚騒動は、文字通り連日連夜の報道だった。
かくいう筆者も当時TV画面にかじりつき、氏の凶行に地団駄を踏んだ男の一人である。実際画面に映し出された若き日の氏の顔写真は、作家と言うよりは俳優に近く、腹立たしさもひとしおだった。これは当時の全ての男性の率直な感想だったのではなかろうか。
“あの頃は若かったですねぇ”と笑う氏は、悔しいことに今なお当世一の美女が選んだのがうなずける美丈夫ぶりだ。何しろ自らを“ミステリー作家”ではなく“推理小説家”と位置づけている男だ。その心意気たるや良し、である。
*****
「あまり着る物に拘る方じゃないんですよ」
若い頃はスパイ映画のスターに憧れて、細身のイタリアンテイストの物を好んで着ていたそうだ。なるほど。あの不敵で官能的なスーツを纏って、かの女性のハートを射止めたという訳か。
今はもっぱらイギリスのクラシックスタイル。
「警察関係の方とか、司法関係の方とか…お堅い方に会うことが多いんで、とにかく信用して何でも話してもらえるためのそれなりの格好、ってのが基本です」
紺またはグレーのスーツに白のシャツ。スタイルは奇をてらわず、それだけに素材や仕立てが本当に良い物を選ぶ。装いがシンプルなだけに、着こなしや小物遊びのセンスが問われるが、これもあくまでドレスコードに忠実に。
時計は信用第一の日本製。靴やベルトなどの革物はご贔屓の工房がイタリアにある。タイはオーソドックスであることが基準。
「日本人ですしね。野暮ったい位の方が相手に警戒心を抱かせない上では有利でしょう」
飾らず気取らずシンプルに、装いは勝負のテーブルにつくための最低限の物でいい。利害が錯綜する犯罪の最前線、“切れる人間”である事を証明するのはスーツではなく中身だ。信頼できる服を誠実に着こなす――それ以上の事は考えないという。
自分のスタイルを確立するコツは、と聞いたら“プロに相談するべし”との答えが返ってきた。
「父の代から付きあってる仕立て屋が、東京にあるんですよ」
うらやましい事だ。親子二代着道楽が続けば、本物のシックも夢じゃない。
「いや。父もこういう事には不精でしたから、全部仕立て屋さん任せだったんです。おかげで僕も手のかかる客になっちゃった。――実は向こうも親子二代続いてるんです。それで、親父さんと息子さんの意見はやっぱり違うんだけど、根底にある指針というか…考え方が一緒なんですよ。そういう店とつき合えるのは、客の方も幸せですよね」
“拘り”よりは“愛着”の方が付き合いやすい。何がなんでも、と言うのでなく時には息子さんの方の意見を取り入れ、時には親父さんの意見に全面的に任せてみる。拘りの持つ一種病的な情熱はなくとも、ふと手に取って眺めたくなる優しさは人を豊かにする。
「拘り、は自分を縛りますよね。僕は根本の所がいい加減な人間だから、しばらくはそういう拘りを楽しめるんだけど、途中でイヤになっちゃうんです。仕事であちこち旅行するせいもあるんでしょうけれど、大きい世界を見ちゃうと、つまらない事で自分を縛り付けてる事がバカバカしく思えてくる」
だからあくまで自分に素直に、愛しいと思った物には素直に手を伸ばす。――それが氏にとっての基本姿勢なのだそうだ。
*****
愛着のある物の一つも持たなければ、人生が浅くなる、と言ったのは開高健だったか。
「エスキモーのナイフとか、戦場の銃とか…確かに物の善し悪しが生命を左右するような場面はありますね。そういう事に対するオマージュとしての拘りは、判ります」
氏の選んだメニューはマティーニ。ヘミングウェイのごとくドライにする事も、ボンドのようにシェイクさせる事もなく、オンザロックで。理由はただ単に、喉が乾いていたから。
「若い頃にそういうカッコつけの拘りを散々やって、すごく窮屈だったんですよ。“武士は食わねど高楊枝”って確かにカッコいいし、若いときはそれ自体が目的だった。そういう拘りがあるいは飽きちゃったり、あるいは30、40過ぎるうちにちょうどいい位に削られたりして、自分の中で本物になってく。…40過ぎたぐらいからですかね。意地張らなくてもまあ自分という物を許せるようになったのは」
若ければそれでも体力でカバーできるが、年を取るとそうそう意地を張ってもいられない。“人間が円くなる”という事は、所詮はそういう事なのかも知れない。
「物って、人の代用なんじゃないかな」
良い物はそれを作った職人の魂が宿る。歴史的な物ならば、それを使った者の残滓がこびりついているのかも知れない。拘る人間は、その匂いに引かれて物を手に取る。
人が人を求める媒介として良い物があるのなら、拘りは人恋しさのような物だろうか。
「禁欲的ですごく色っぽい関係ですね。大人の贅沢だ。僕はまだ悟れてないから、一直線に人間の方に行っちゃってる」
物語は現実から生まれる、というのが氏の持論。本当に起こっておかしくない物語に、現実には果たすことのできないカタルシスを加味する。それが個性的な名探偵であったり、神出鬼没の怪盗だったり…。
だから新しい物語を生むためには、人との出会いが不可欠なのだそうだ。人と会って、その人の中の拘りや愛着を受け入れるには、自分は白紙の方がいい。ただ誠実である事。その人の心情をなぞり、感情移入した上で、その情熱の根元を見極める。
「スイスの時計にせよ、イタリアのスーツにせよ、たとえばアラブの砂漠の中じゃ何の役にも立たないでしょう。それでもいい物は目を引くのかも知れないけれど、どんなに高価なベネチアングラスよりも、砂の上なら素焼きの碗の方を取りたいですよ。人があって場所があって物がある。そこにようやく拘りという物が発生する。僕が拘るとしたら、その丸ごと全部にでしょうね。だからイタリアのワインが飲みたいときはイタリアに行くし、いい軸があれば上海の別荘に飾っておく」
最後に“男にとって最高の拘りとは”と聞いてみた。
「己の命を賭けても守りたい女性、ですかね」
20年前の伊達男は、今をもって健在のようである。