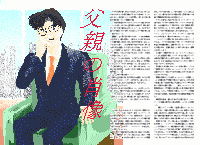
昨年『父と息子』というタイトルで特集を組んだ時、高校生探偵・工藤新一君のインタビューを行った。テーマとして読者世代の心に適う内容であったためか、非常に大きな反響をいただき、ぜひ一度父親サイドのインタビューもというご意見が多数寄せられた。
インタビュアー・構成:勝谷陽介
私個人としてもぜひ一度お話を伺いたかったが、大変多忙な方であるため予定がつかず、今日にまでずれこんでしまった。この大作家のインタビューは本誌にとっていわば念願であった訳だ。
お会いした工藤氏の開口一番の台詞が「実は息子はあなたのファンなんですよ」だった。――聞けば息子さんの書棚に私の著作が何冊か並んでいるという。「あの時(インタビューの時)はそれもあってついベラベラと話してしまった、と後から落ち込んでいました」とつけ加えた。だから私もぜひ一度お会いしておきたかったとおっしゃる。
息子の書棚の中身に目配りのできる父親は、貴重な存在ではないかと思う。
―――以前息子さんのインタビューをさせていただいた時、すごく大人びた子だな、という印象だったんです。ただ単に礼儀正しいって言うんじゃなくて、経験に裏付けられた自信とても言うのか。周囲全部大人に囲まれて、マスコミの矢面に立って刑事事件に関与してる訳じゃないですか。そういう事が可能になるためには一体どんな教育があったのか、っていうのがすごく知りたかったんですね。で、本当に小さい頃からすごく多様な経験をさせてもらった、ってのを聞いて「ああそういう事だったのか」と。それは意識してらっしゃったんですか?工藤:最初は妻の方がそういう事には熱心だったんです。ハリウッドで仕事をしてきて、良くも悪くもアメリカ的な自由と平等を肌で知っていたからでしょうか。息子はイギリスで生まれたんですが、ベビーシッターを頼むのでもナイジェリアからの留学生やら、チガーノやらと…あちらの常識では考えられないような人種の方にお願いしてました(笑)。私も取材で色々な人にお会いする機会が多いので、小さい頃から沢山人を見て育つのは悪い事ではないな、と。0歳段階から色々な人種に揉まれて育った人間と、三十代で初めて黒人に会った人とでは人に対する柔軟度が違うでしょう。できる限り柔軟な人間に育って欲しいとは思っていましたね。―――内戦中の国だったり、インドやアラブにも連れていったりされてたんですよね?工藤:あの子は結婚から月足らずで生まれて来まして(笑)。ご存じのようにほとんど駆け落ちに近い結婚事情でしたから、お互い離れるのが不安だったんです。それで妻が私の取材に同行する事が多くて。で、乳飲み子の息子も連れて危険地帯へ(笑)。それもあって、平等・博愛精神を教えるのが妻の役なら、危機管理を教えるのは私の役だろうと考えたんです。
あの子は覚えてないでしょうが…アフリカの民族学フィールドワークに付き合わせた事があるんですよ。ナバホ族とか、唇に大きな皿状の物を入れて身体改造する部族があるでしょう?子供だから最初は怖がって大泣きするんですけど、二回目には慣れるんです。同じ年頃の子供もいますしね。
見慣れない人間がいれば誰でも警戒するし、怖ければ防衛する体勢に入る。子供は正直だから、相手が臭かったり汚かったりするとすごく警戒するんです。そうじゃなくて、本当に危険な人間を見分けるカン、みたいな物を教えなきゃならないと思っていました。これはもう知識じゃ追いつかない本能レベルの物かもしれないけれど。―――それは国際人として通用するための教育だったんですか?工藤:日本みたいな平和な国であれば「知らない人に付いて行っちゃダメ」程度で済みますが、海外だと自衛意識が薄いのは致命的です。あの子が生まれた当時は英国に住み続けるつもりだったので、それなりの教育はしていました。そういう危機管理って、生き残る上で一番重要じゃないですか。明らかに自分と違った種族とも友好的なら関係を保って生活していかなきゃならない。どんなに自分と同じような身なりでも危険な人間は避けなきゃいけない。
危ないと思った所には踏み込まないことや、単なる物取りなら小銭を与えてやればいい事なんか、その場その場の判断ですよね。それを雰囲気や流れから読みとれるだけのアンテナは持って欲しいと思いました。まあその結果が私自身が危険を感じるような場所への同行だったんだから、親としては最低だったんでしょうね(笑)。―――でも守り切るおつもりだったんでしょう。工藤:妻共々ね(笑)。でなきゃ結婚してません。とは言え、今思えばよくまあこんな無茶な男に付いてきてくれたものです。海外で仕事してて、自意識をきっちり持ってる女性だったのが良かったんでしょうかねえ。
普通はそういう危険のない場所に子供を囲い込んで、危ない所は行っちゃダメだと言い聞かせて育てるんでしょうけどね。自分の経験からちょっとそれは違うと感じていた物ですから。
―――少し工藤さんご自身の事を伺っておきたいのですが…。16歳で単身ヨーロッパに渡られたと聞いてますが。工藤:生意気盛りでしょう、その年頃は(笑)。家出同然に飛び出して、それこそ一旗揚げてやろう、国際人になってやろうみたいなノリだったんですよ。家が割と厳格な家だったんで、人一倍反骨精神旺盛だった。こんな狭い国で縛り付けられてるのはイヤだとずっと思ってて。好奇心強くて後先見ずな性格でしたし(笑)。で、実際日本を飛び出してみて、すごいカルチャーショックだった。
ヨーロッパというのは厳格な階級社会で、アジア・アラブ人は人間の部類に入ってないじゃないですか。どんなに金を持っていても白人じゃないから入れない店がある。目に見える形で差別があるんです。日本でそこそこの家庭で育って、それなりに大切にされていた所からそういう所への落差ってシャレにならない位大きいでしょう。生意気盛りのガキが現実突きつけられて、途方に暮れるしかなかった。
その時にものすごく考えたんですよ。大きな大陸で色々な種類の人間が混じり合って暮らすって事はどういう事か、って。日本みたいな単一民族が島国で暮らしてるのとは訳が違う。どんな形であれ特権階級が既存権を守ろうとするのは必然だし、社会からはじき出された人間が犯罪に手を染めるのも一種の必然なんですね。そういう人間社会の成り立ちみたいな事から考えさせられて…。んじゃあオレはできるようにしか生きられないんだな、と開き直って。そこから坂道を転がるように悪の道へ(笑)。あの頃の私はどう考えても犯罪者でしたね。―――犯罪者、ですか?工藤:ええ、とにかく非合法すれすれの所を歩いてました。警察と地元のシンジゲートの両方から目の敵にされて、割と何度も死にかけてるんですよ。その土地にいられなくなる位ヤバくなると逃げ出して、最後にたどりついたのが西海岸の非合法探偵(笑)。もう映画みたいな人生でしたね。時効だろうから白状しちゃえますけど。―――前のインタビューの時、息子さんが「お父さんは怖い人だ」と言ってらしたんですよ。それはそういう事からくる物なんでしょうか?工藤:そうですね。息子みたいな人間からすれば、私は「何考えてるか判らないキレたら怖いヤツ」って事になるんでしょうね。あの子といるとその辺りの感覚のズレが面白い。
―――小説家としてデビューされたのが23歳。工藤:22の時に日本に帰ってきて、それからまもなくでした。やっぱりもう向こうに居られなくなって(笑)。それで舞い戻ってきて探偵とは名ばかりのイザコザ屋をやってました。依頼があって気が向けば、どんな危ない話でも乗るような。
思えばあの頃が一番傲慢だったかもしれない。オレはお前らみたいに安全な場所でぬくぬく生きてたヤツとは人間が違うんだ、みたいな鼻持ちならない所がありましたね。映画のヒーロー気取りで自分からトラブルに突っ込んでったりしてね。小説書いたのって、自分の理想のカッコいい男を書いて周囲を啓蒙してやろう、みたいなノリだったんです。自分に絶対の自信があった物の、それを証明する術がなくて「結局自分はただのはみ出し者の落伍者じゃないのか」みたいな感覚も持ってました。
そういう状態の時に妻に会ったんです。妻の方もハリウッドの頂点まで上り詰めて、どこかしら不安を抱えてた時期だったんでしょう。一目会ってお互いに「同類だ」と思いこんじゃったみたいなんですよ。もう歯止めも何もあったもんじゃなかった(笑)。―――ものすごい騒ぎでしたね、あの時は。工藤:人気絶頂の女優でしょ。普通なら手の届く人じゃないと思って諦めるんでしょうが、向こう見ずな性格ですから(笑)。迎えに来た彼女の車に追突して、そのまま彼女さらって逃げちゃったりとか、マネージャーのフリして呼び出して一日引っ張り回したりとか(笑)。今で言う所のストーカー犯罪ですよね。彼女に嫌われてなくて本当に良かった(笑)。―――…ずいぶんご苦労されたんですね。工藤:毎回命がけでしたね。この機会を逃したらもう二度と会えないかも知れない、って感覚でしたから。彼女と一晩過ごせるなら、刑務所に放り込まれても本望だと本気で思ってました。で、会うたびに「今日こそはプロポーズするぞ」って気合い入れるんですが、いざ彼女の顔見ると一言も口に出せないんですよ。もし断られたらこれから先の一生どうやって生きてくんだ!って(笑)。それくらい本気でした。
玉砕覚悟でプロポーズして、駆け落ち同然に結婚して、息子が生まれて…。本当に地に足がついてないような日々でしたね。…今もそうかも知れない(笑)。―――今も恋愛継続中ですか(笑)?工藤:いい歳して何のろけてるんだ、と笑われるでしょうが、やはり運命の女だなと思っています。生まれながらの同族、とでも言うんでしょうか。私がどんな非常識をしでかしても、妻だけは判って受け入れてくれるような確信があるんです。こういう女性に巡り会えた事そのものが、もう本当に奇蹟としか言いようがない。天の采配だとしたら、私は運命に恵まれたんだと思います。
息子は、その妻が与えてくれたもう一つの奇蹟でしょうね。たとえ私の作った作品全てがこれからの時間の中で忘れられてしまっても、あの子だけはこの世に残る。私という人間がこの世に生きた唯一の証かも知れない。
―――その大事な息子さんとは、中学の時に別居されたとか。そのあたりの事情というのはどういう事だったんでしょう?工藤:その前の年に「闇の男爵」の日本での刊行が決まってたんです。それまで私はずっと海外相手に作品を書いてきて、日本じゃ作家としては無名に近かった。まあ、一部の推理マニアの間には浸透していましたけどね。それがアメリカの版元が日本に進出する形で「闇の男爵」の翻訳版を出す事になった。あの作品はシリーズ物でボリュームもあるし海外での評価も高いから、版元としては大々的に売り出す気でいたんです。
中学に入ってから、あの子はあまり私に近づかなくなってました。親の言う通りに動くんじゃなくて、自分で動く事を覚える年頃でしょう。そういう時期に父親が有名人の仲間入りしてしまうのは非常にまずいと感じたんです。それでなくても母親の名前のせいでイヤな思いもしていたみたいですし。
最初は親子共々ロスに住む事を考えてたんですが、あの子が乗り気じゃなかった。私も一番多感な時期に、親の都合で慣れた環境から離すのは惨い事だと思っていた。それで冗談がてらに「一人で暮らすか?」と聞いたら「それもいいね」と。―――息子さんがそうおっしゃったんですか。工藤:半分以上冗談のつもりだったんでしょうけどね。まさか本気で置いていかれるとは思ってなかったと思いますよ(笑)。当時から私は取材なんかで年の半分も家にいない風でしたけれど、母親が居て家政婦さんがいて、ごく普通の子供でしたし。
で、14歳の誕生日に日本の家をあの子の名義に書き換えたんです。もちろん18歳までは代理人である弁護士が管理してましたが、18歳で正式に譲渡が成立しました。同時に生活費一切合切をあの子の口座で管理するようにして、所得税・住民税から生活費一切、全部あの子の名義でやる事にした。―――息子さんが中学生、でですか?工藤:ヨーロッパの上流階級だと、それ位の年から親の財産の一部の管理を任されますよ。もちろん実務は会計士や管理人がやるけれど、最後に報告書に必要なサインはその子の物であるようにする。責任を持たされるんですね。
子供って二十歳を境に大人になる訳じゃないでしょう。大人の責任を背負う前に、試行期間を取るべきだと思うんです。14歳になった。じゃあ自分の生活を自分で管理してみなさい。自分が毎日生活していくのにこれだけお金がかかるんだよ、公的にはこれだけの手続きが必要になるんだよ、家政婦さんや弁護士さんとはちゃんと付き合わなきゃいけないよ、と。それを現実として教えておいて害はないと思うし、それ位の事は親が環境を整えてやればできると思うんです。日本でも昔はそうだったんじゃないですか。ある程度の年齢になれば、家庭の中で責任の一つも割り振られていたでしょう。―――しかし、いくら何でも不安じゃありませんでしたか?なんと言っても未成年な訳ですし。工藤:都合でやむを得なかったとは言え、やはり重い物を負わせてしまったという自覚はありました。その分とにかく周囲には気を使いましたね。ご近所の方に事情を話して、何かあったら連絡いただけるようにしましたし。警備会社にも24時間体制での警備をお願いしました。かかりつけの医者にはロスとホットラインで繋がるようにして、私が世界中どこにいても、必ず1時間以内に連絡が付くようにと。もよりの警察署にも挨拶に行って、こういう事情ですからとお願いしてきましたし。
頭の中だけで大人になって欲しくなかったんです。自分を確立する年頃でしょう。私が与えた経験や知識から、あの子なりの社会の外形を掴もうとしていた。そういう時、知識だけじゃなくて体で経験していく事って絶対必要ですよね。自己管理意識・危機意識って、地に足がついてないとしっくり馴染まない。とりあえずは体調がおかしい時、寝てれば直りそうだけど一人暮らしだから医者に行っておこう、みたいなレベルの知恵から付けて欲しかったんです。
判らない時はとりあえず安全策を取ることや、自分の手には負えないときちんと判断できる事、必要と思ったら迷わず他人に助けを求める事なんか、当たり前だけど絶対に必要な事です。訳が判らないまま口をつぐんでいて、気が付いたらものすごく危険な場所だったって事が日本ではありうる。
だから別居して一番最初に、ロスにあの子から電話をかけてきてくれた時は本当に嬉しかった。中学生で一人暮らしで、心細くないはずがない。それをちゃんと吐き出せるかどうかはものすごく重要だった。だから「別に用事はないんだけど、そっちどう?」って電話してきた時、ああこの子は大丈夫だとようやく安心した。他愛ない話をして切った後で、妻から「一生そのまま舞い上がってなさい」と言われた位(笑)。―――息子さんのインタビューの時に「ああ、これは普通の家庭じゃないな」と思ったんです(笑)。普通の家庭って、男の子だと特に父親との軋轢の中で自分を自覚していくじゃないですか。小さい頃から内戦やってる国に連れていったり、犯罪の現場に連れていったり…とにかく自分で考えさせようとなさってた。絶対自分の考え方を押しつけない。その上で非常に息子さんを溺愛してらして、自分の持ってる物を何もかも与えようとする。
今日お話を伺って、何もかも息子さん本意で考えてらっしゃったというのがよく判りました。ご自分の存在が息子さんにどう影響するかまで考えてらしたんですね。工藤:そういう風に接していた事自体が、私のエゴだったと言えなくもないですね。世に言う「頑固オヤジ」だった方が、あの子にとっては楽だったと思います。ただ私自身父とケンカしながら成長しましたから、あの子が自分みたいな人間に育つのはちょっといただけないかな、と(笑)。
私も妻もこういう商売ですから、沢山の人間の視線がどういう力を持ってるかは骨身に染みています。息子は生まれながらにしてその力の影響を受けなきゃならない場所にいた。それこそ世界が綿菓子でできてるような年齢で、ですからね。これに関してだけは本当に申し訳なかったと思っています。贅沢させて育てたのは、その埋め合わせみたいな物ですね。
どこの親御さんでも一緒でしょう。側にいることがためにならないと判断すれば、親は子供から離れるんです。翻って言えば、それ以外で子供を手放す親はいないでしょう。子供を潰すと判断できても、離れられない親だっている位ですから。
―――高校生の時に「死んでもいいぞ」と言われたんですよね?僕はその時我が身を顧みて絶対言えない台詞だと思ったんです。死んでも口にできないと思う。工藤:高校生探偵でしたからね。いずれそういう事にもなるだろうと覚悟していましたが、実際そうなってみて認識が甘かった事を悟りました。冷静でいられるつもりだったんですが、もう生きた心地がしませんでした。
あの時は…当時息子が関わっていた事件というのが、歌舞伎町あたりを拠点にした外国人犯罪結社に繋がっていて、警察も迂闊に手出しできないような領域がすぐそこまで迫ってるような状態だったんです。あの辺りには、10万程度の金で殺人を請け負う外国人がゴロゴロしてるでしょう。顔も名前も知られてる息子にとっては、とにかく危険この上ない状況だったんです。ロスに来るようには言ったんですが、あの通り責任感の強い子ですし。自分の蒔いた種を自分で始末したいからと聞き入れてくれなかった。
幸い後ろ盾になって下さっていた方がいて、そう簡単には危害が及ばない形にはなっていたんです。それで組織検挙の証拠固めをやっていた。もちろん私もバックアップしたし、警察の方にもご協力をお願いしました。台湾や香港の警察・軍にも協力をお願いしました。
これはあの子には内緒だったんですが、万一に備えて夫婦でしばらく東京近郊の貸し別荘に住んでいたんです。あの子の居場所を知られないためにも、側にいる訳にはいかなくて。だからって何か起こってロスから駆けつけると12時間はかかってしまう。表向きロスの自宅にいる事にして、私立探偵時代のコネをフル動員して何とか検挙できるだけの材料を揃えようとしたんです。
必死でしたね。…それでも最悪を覚悟しなきゃならなかった。―――言った時はどんなお気持ちだったんですか?工藤:我ながら酷い親だな、と(笑)。でもそういう風に育ててしまった以上、責任はとらなきゃいけないな、と。実はあの台詞には続きがありましてね。「お前が納得できる死に方なら死んでもいい。けれどもし不本意な死に方をしたら、私は犯罪者になるから」と。
司法に裁きを任せるなんて事は、私にはできないだろうなと自覚しました。人間ができてないんでしょうね。今でも多分そうです。もう息子も二十歳近いっていうのに子離れできてない(笑)。みっともない話です。―――息子さん、自分が死んだら父は相手を八つ裂きにするだろう、とは言ってらっしゃいました。工藤:本当に何をするか判りませんでしたね。不条理な形であの子を奪われるような事になれば、自分を含めた世の中全部を呪ったと思います。それこそ八つ当たりで車でビルに突っ込んで、火ぐらいつけたかも知れない。…困った極道親父だ(笑)。
安全な場所へ拐っていく事はできたんです。力尽くで言うことをきかせる事もできた。でもそれでは息子が壊れてしまうのが判ってました。私自身、書くことと人に会うことを止めたらバランスを崩すだろう人間だから、それは血筋みたいな物でしょう。
本当言うと、高校生探偵には最初から反対だったんです。もっとあの年齢でしかできない事をして欲しかったですね。女の子と恋をしたり、友達と殴り合いのケンカしたり、バイクで暴走してくれても良かった。あの年齢でしかできない豊かな感情を経験して欲しかった。冷静を繕って大人の中に立つ事はこの先いくらでもできるんだから、もっと今しかできない事をしなさいと言いたかったんですが…。そういう風に育ててしまったのは自分ですしね。
私が投げかけ続けた物に対する、息子なりの返答だと思うんです。だから止められなかった。腹をくくるしかなかったんです。
―――死体を棒でつついても叱られなかったというのを聞いて、ものすごく驚いたと同時に納得もしたんです。子供って本来そういう物なんですよね。蝶の羽根をむしったり、小さな動物を殺したりする。それって本能に近い衝動だと思うんです。それでたとえば飼っていたペットが死んだり、肉親が死んだりした時に、それがどういう事だか悟る。でも親としては社会的にそれを黙殺する態度は許されない訳でしょう。社会通念を追いやっても、自分の考えを押しつけない事を取られたんですか?工藤:あれは…息子に「どうしてしちゃいけないの?」と聞かれた時、私が答えられなかったからってだけの話です(笑)。自分がされたら嫌だろう、というのは問題のすり替えでしかありませんし。人道に反するから、なんてのは間抜けな言い訳ですしね。それこそ「死神に祟られるから」と言ったほうが、よっぽでしっくり来るし生きる上でも知恵でもある。
こういう職業をやっていると、ヒューマニズムという物の薄っぺらさを嫌でも思わざるを得ない。見慣れない人間がいれば警戒して当たり前だし、恐怖を感じて当たり前じゃないですか。ヒューマニズムというのはそういう生理的な感覚と相反する概念なんです。しょせんあんな物は絵に描いたモチで、大人が欲しがるファンタジーでしかない。
形から教える事はできたかもしれませんが、自分が信じてもいない物を子供に教えたくなかったんです。「悟る」とおっしゃいましたが、まさにその通りですね。親は子供が考えるための材料を与えてやるだけでいい。
小学生で殺人現場に連れて行ったのも、どちらかと言えばそういう事の延長でした。人が死ぬ、というのがどういう事なのか、自分で見て判断して欲しかった。―――それで小さい頃からお子さんを現場へ?工藤:ああいう事件って、譲れない利害の線上で起こるでしょう。一番人間という物の本質が知れてしまう。それを具体的な形として見せたかったのかな。あまり見目いい形じゃありませんが、それでも何より見て欲しかった。―――最初に連れていかれたのが小学校4年の時と伺ったんですが…息子さんがそれで傷つくような事は考えられなかったんですか?工藤:日本はこういう国だから人の死が歴然と見えませんが、アラブ諸国なんかだと、もう日常に死が転がってますよね。あえて言えばそんな事で傷つくようなヤワな神経に育って欲しくなかったって所でしょうか。銃で撃たれたり刃物で刺されたりすれば死ぬのと同じで、絶えきれないような出来事に見まわれた人間はバランスを崩してしまう。そういう心の弱い部分や醜い部分をきちんと受け止めて欲しかったですね。恥じても隠していてもいいから、そういう傲慢や凶暴が自分の中に潜んでいる事を自覚して欲しかった。
中学で現場へ着いてこなくなった時は、それが“不可触な領域”だと悟ってくれたんだとばっかり思ってました。生半可な覚悟で触れてはいけない領域だし、普通に生活してる人間が触れていい領域じゃない。年齢と共にその辺りの感覚を理解してくれたんだと思ってたんですが、どうやら逆だったらしい(笑)。
あの子にとっては、それが人間と付き合うための窓口になってしまったみたいですね。絶対誤魔化せない本質部分に、ざっくり切り込んでいく事を選んだようです。一本気で少々せっかちな子だから、そういうやり方になってしまったのかも知れません。…そのあたり、私があの子に敵わない所でしょうね。
―――さて、最後の質問ですが…息子さんの事を何割ぐらい理解していると思ってらっしゃいますか?この本の読者層の父親たちに、ぜひ聞かせていただきたいのですが(笑)。工藤:うーん。98%って所ですかね。自惚れで「判ってるぞ」と思い込んでる割合も含めて(笑)。―――ちょっと聞けない数字ですね(笑)。自惚れは何割ぐらい?工藤:さあ(笑)。まあでもこれ位言えなきゃ、探偵なんかやらせていられませんよ(笑)。―――それにしてもすごい数字だ(笑)。親子の断絶に悩む世の父親達にアドバイスしていただけませんか。どうやって息子に接すればいいか?工藤:日本の父親は背中で語りますからね(笑)。作家みたいな一種のはみ出し者的な職業だと、背中じゃ語れない。世界に背を向けて原稿書いてるだけの欠陥人間になってしまう(笑)。
背中で語るにせよ言葉で語るにせよ、子供の前で出し惜しみするようなマネはしちゃいけないと思います。愛情も注意も、注げる限りは注いでやるべきだと思う。それこそ親の威信にかけて、与えられる限り与えてやりたい。どこの親御さんもそんな事当たり前に考えてるんじゃないですか。形はそれぞれでしょうけれど。
向こうが言葉にする事はきちんと受け止める、投げてくるサインは必ず拾う。向こうが「カンベンしてくれ」って言うまで「愛している」と言う。…私が言えるとしたらそれぐらいですかねえ。―――それぐらい(笑)?工藤:ええ。父親なんてそれ位しかできない(笑)。
妻はあの子が生まれた時、“この子は私たちみたいな人間には育たないだろう”と直感したと言ってました。私はあの子が物心つくまで、自分そっくりの人間になるんだと信じてましたよ。だから火の起こし方とかナイフの使い方とか…人外魔境に放り出されてもいいようなサバイバル知識を詰め込んでた訳です。あの子が社会という物の中で上手に生きていける人間だと判った時は、かなりショックでした(笑)。絶対私や妻と同じく、はみ出しちゃう人間だと信じていたのに。
家族って、血の繋がりって言うよりは、それに付随する思いの繋がりでできてる物だと思うんです。親と子供は違う人間だし、もしかしたら人間の種類まで違ってるかも知れない。全部都合良く噛み合うなんて、絶対ありえないんです。だから家族でいる努力をしない家族は家族とは言えなくなってしまう。それがイヤなら“思い”の部分をきちんと伝えなきゃいけない。息子に対して物惜しみするような親にだけは、私はなりたくないです。
動物ならいざ知らず、人間は血のつながりで全部解決できるほど簡単にはできてないでしょう。足りない分は行為と言葉と注意で補っていくしかない。―――どうも今日は貴重なお時間をありがとうございました。工藤:語る対象が自分じゃないインタビューは気楽でいいですね。楽しませていただきました(笑)。
世界的なベストセラー作家に相応しく、非常に“気配りの人”“サービス精神旺盛な人”という印象を持った。本誌のターゲットは30代からの男性。編集サイドとしては、既存のグラビア雑誌とも活字雑誌とも違う“大人の男の総合情報誌”を作るつもりでいる。そのコンセプトをきっちり読んだ上でお話しいただけたのだと、活字に起こされた物を見ながら唸った。実に油断のならない人だと思う。
強い人である。世界全てを敵に回しても、妻と子供を守る気骨のような物が言葉の端に読みとれる。「運に恵まれた」とおっしゃったが、運を味方に付ける人間独特の覇気のような物が感じられた。紳士然とした風貌の下に、とてつもない大きな力を隠し持っている。根底の所で無法というかワイルドと言うか…力づくを押し通す我の強さが透けて見えていた。「高校生探偵には最初から反対だった」と言う彼が、それでも息子の行動を見守るに徹したのは、自身の強さを息子の中に見ていたからではなかろうか。
子供に対して出し惜しみはしないというのは、大切な事だ。不器用だ何だと言い訳し、父親の威厳を塗り固めているうちに子供は気付いて去っていく。“死んでもいいぞ”と言えるほどの度量は見せられないにしても、与えられる限りの物を与える態度は見習うべきだろう。誤解されてもみっともなくてもいいから、自分から手札を晒せるだけのしたたかさは、親としてあるいは理想かも知れない。
先の対談からずっと、工藤新一を非凡な子供だと思っていた。今回優作氏にお会いして、決してそうではないのだと判った。有名人の息子だからと言って、彼は何一つ特別な育てられ方をしていない。ただ彼本人に対して非常に忠実に育てられた。周囲の誰にも押しつぶされる事なく、生来の彼のままであの年齢になった。――世間的に大いに認められた父親の側で、そんな風に育てられたのは本当に幸福な事だと思う。
これで息子の側と父親の側の双方のインタビューが出そろった。恐らく優作氏の気遣いによるのだろうが、非常に似通った方向性の対談が二つできあがった訳だ。読み比べて非常に面白い対になっている。親子や家族というものについての実に深い示唆に、読者諸氏のご判断をお願いする。