 > >
|
 「放送禁止歌」 森 達也 (監修)デーブ・スペクター
【解放出版社】 「放送禁止歌」 森 達也 (監修)デーブ・スペクター
【解放出版社】
|
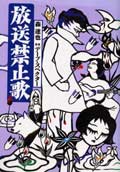 テレビなどを見ていると,たまにゲストの誰かが,「おやっ?」と思うような発言をする。でもその場はそれで過ぎ,番組の最後の方で「番組中に不適切な発言がありましたことを深くお詫び申し上げます。」などと司会者やアナウンサーがいう。こういう場面を見たことのある人は多いのではないだろうか。
テレビなどを見ていると,たまにゲストの誰かが,「おやっ?」と思うような発言をする。でもその場はそれで過ぎ,番組の最後の方で「番組中に不適切な発言がありましたことを深くお詫び申し上げます。」などと司会者やアナウンサーがいう。こういう場面を見たことのある人は多いのではないだろうか。
こういう番組を見るたびに,「何が不適切なのか,みんな分かっているのだろうか?」といつも疑問に思う。説明もなく形式的な謝罪と訂正の言葉で,根本は解決しない。 著者の森達也さんはフリーのテレビディレクターとして,「放送禁止歌」なるものの存在に疑問を持ち,その生まれた背景を探っていく。 結論は,自主規制,それも「巨大な共同幻想である自己規制」である。「放送禁止歌」なるものが存在するわけではない。「この歌は,禁止だったかなぁ」→「わからんけれど,やめておこう(抗議がくるから)」といったような短絡的なメディアの思考が背景にある。すなわち無自覚,無責任な自己保身である。みな「自分の頭と言葉」で考えていない。 このことは,日々いろんな場面で感じることがある。「○○が言うから」「(慣習で?きまりで?)こうなっているから」・・・など。 もう一カ所引用する。(P163) 「差別の内実は変わっていない。その現実はふまえながらも,でも怯えてもいけないのだと思う。放送禁止歌という存在が象徴するように,僕らは視界を自ら狭めて思考を停止させてしまう傾向がきっとある。見ることなく,聞くことなく,したり顔で語ってしまうことがきっとある。見ればよい。聞けばよい。話せばよい。知ればよい。それだけで視座は確実に変わる。それだけは間違いない。」 この本で焦点の一つとしてあげられている岡林信康の『手紙』『チューリップのアップリケ』,高田渡の『生活の柄』などの曲が入ったレコード(LP)が,なぜか我が家にあった。そういったこともあってか,解放出版社の本のなかでは,すーっと一気に読むことができたた。 |

| 森「……部落差別について,デーブはどう思ってる?」 デーブ「日本的な差別だよね。外見上は全然差異がない。文化や習俗にも差異はない。 つまり,宗教や民族などが差別の要因ではない。こんな差別は世界でも珍しいよね。」 森「どうして消滅しないのだろう?」 デーブ「日本人の君がシカゴ生まれれの僕に聞くの?個人的な見解だけどこのままじゃ難しいよ。なぜなら僕が日本に来ててからの印象だけでも,部落差別という問題はどんどん,……何ていうのかな。潜っていってるという印象が強いよ」 森「潜る?」 テーブ「そう,人に意識の下に。あるいは社会の制度の下に」 森「なぜだろう?」 デーブ「簡単には比べられないけど,黒人差別にに反対する運動に立ち上がった人は黒人だけじゃない。南北戦争もそうだし,公民権運動以降,差別される当事者の黒人側だけでなく,差別する側の白人が,自ら問題提起をし始めたときに運動の展開は大きく変わったんだよね。でも部落差別の問題を提起するのは,多くの場合,差別される側,つまり解放同盟しかいない。差別って,差別される側じゃなくて差別するほうに問題があるわけじゃない?差別する側の方がもっともっと現状についての認識を深めて,主体的に運動に参加していくのなら状況は変わると僕は想う」 しかし差別する側の認識や,啓発に大きな力を持つはずのメディアの意識は絶望的なまでに低い。・・・(中略)・・・ 数年前,大阪の被差別部落を,テープは一人で訪ねている。別に具体的な仕事がらみではない。「朝まで生テレビ」で一緒に話した野坂昭如に「日本のメディアで働くからには一度は行くべきだよ」と薦められ,まったくその通りだと同感して解放同盟大阪府連合会に連絡し,訪ねたのだという。 デーブ「その時にとりたてて新しい発見をしたというわけではないよ。でも,実際に街を歩いた経験は,僕にとっては大きいよ。なぜなら偏見や妄想は,知らない人に生まれるんだから。でも僕は,実際に部落内を歩いたし,そこで何人もの人たちと話もした。 この体験は重要なことなんだよね。特にメディアに携わる人なら,誰もが自発的にやるぺき行為だと僕は思う」 そこまで言ってから,シカゴ生まれのユダヤ人で日本人の妻を持つテープはにっこりと微笑んだ。そろそろジョークの時間かなと僕は思う。しかしその予想は外れた。いつもの早口とは別人のように,テープはゆっくりと,一語一語を噛みしめるようにこう言った。 テーブ「放送禁止歌と同じだね。大切なことは知ることだよ。見て,触れて,感じることなんだよ」 (P128〜P130より抜粋) |
