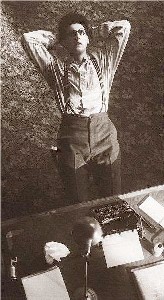341 関 係
04/03/10 |
 |
夫婦という関係も結婚30年ほども経過してくると、なにかマンネリというかうんざり、どうでもいい、仕様がない、はたまたすれ違うというような感じにもなってきているのに気付く。ぼくも連合いも今年でなんと53歳になってしまう計算。ぼくら、けっこういい感じで恋愛もしたし、結婚も。子供も4人でき、皆健康に暮している。
『慣れ』というのだろうか『飽き』というのだろうか、『遠慮』がなくなった。でもいまさらそんなことばを持ち出すまでのこともないような気もする。昨年2人の孫ができた(長女・次女の)ことが原因だろうか。連合いは孫との付き合いで相当いそがしいようで、そちらに気持ちが行っているからだろうか。けれどこれはちがう気がする。気付いてみるともう少し前からのようだ。(男性にもあるような気もするのだけれど)更年期という密かな波が寄せてきているのだろうか。40代の内にはこういうことはなかったような気がするのだけれど。
藤沢周平の何とか言う短編に、長年の連合いとの関係に危機感を持ちながらも、どうしたらよいのかを探ろうとする話があった。主人公の男は最近妻のいびきが気になり、それを指摘してしまって妻と喧嘩をしてしまう。気付けば最近やたらと喧嘩ばかりしている。もしかすると、本来気の合う者同士ではなかったのじゃないだろうか。この場に及んで、いったいどうなるのだろう、と考え込んでしまうのだった。
考えてみると、なんとなくこの短編に出てくる夫婦とぼくらとはとてもよく似ているような気がする。けっこう些細なことが原因で喧嘩をしてしまう。一日中同じ仕事場で顔をつき合わせているからというのもあるけれど、それはなにも今に始まったことでもない。気付けばもう20年以上そういう日常を続けてきている。いろいろ考えてみてもやっぱり明確な答えが出てこないのはどうしてなんだろう。
藤沢周平の短編では、主人公の男は最後にこんな結論に行き着くのだった。もともと気持ちのぴたりと合う関係などはめったなことではないもの。だとしたら、こういう風に口げんかをしながらも、日々を過ごして行くのもそれはそれでまたいいんじゃないか、と。そんなわけのわからない結論にたどり着いて、男はなんとなくほっとするところでこの物語は終わっている。
なんとなくわかったような気もするのだけれど、それともこういうことなんじゃないか。もしかするといろんなことが分かってきたからなのではないか。かつてはお互いを「こうかもしれない」とか「理解しあいたい」と思ってすごしてきたのかもしれないのだけれど、今になってきて「わかってきた」のかもしれない。
ただしここで『言葉の綾』を持ち出すとすれば、それを「わかってしまった」と思うのか、はたまた「わかることができた」と思うのかのちがいは、実はとても大きな違いなのかもしれないということ。人生にあきらめる気持ちも必要なのかもしれないけれど、それでもやはり付き合ってゆくというのならば「わかることができた」と理解したほうがずっと幸せなようなきがする。まだまだ連れ合いとは長い付き合いになるのだから。
|
342 舗装道路
04/03/17 |
|
むかしぼくがまだ小学生になって間もないころだったか、岡崎市にまだ路面電車が走っていたころ。その路面電車の走る目抜きの通りでさえ、道路はでこぼこだった。当時はアスファルトを路面に流しローラーで均すだけの簡単な舗装だったので、いったん小さな穴ができるとその穴はしばらくして20〜30cmほどの穴ぼこへと成長するのだった。だから舗装が古くなってくるとそういった穴がそこかしこに数え切れぬほど増えてゆくことになる。
時々思い出したように補修工事が行われるのだけれど、それらの穴をアスファルトで埋めるだけという貧弱なものだった。だから今ぼくらが自動車ですいすい道路を快適に走るようなわけにはゆかず、運転手はいつも道路のでこぼこを気をつけながら走らなければならないのだった。ちょっと油断すれば自動車の腹を擦るだの、大揺れのため乗客を含めすべての車中のものがひっくり返るということにもなりかねない。
自動車で走るについてはそれでよかった。けれど自転車ではそういうわけにはいかない。障害物レースよろしく、穴に落ちないよう、また路肩のアスファルトの切れ目から外れないよう、これもまた注意して走るということになっていた。自転車は穴をよけながらふらふらしながら走り、自動車はいつふらついた自転車を引っ掛けるか知れないというので、これもまた気を使いながら走るのだった。
雨でも降れば、そのひとつひとつの穴ぼこに水が溜り、車も人も自転車も油断のできない往来ということになるのだった。まず水がじゃまをして穴ぼこの深さがわからないから、往来にはさらなる注意が必要となる。歩行者、自転車は後ろから近付いてくる自動車の気配には、とくに気を配っていなければ、最悪泥水を跳ね飛ばされることにもなりかねない。そういう意味での注意力はさすがだった。
夏ともなるとアスファルトの黒い路面はしっかりと灼熱の太陽光線を受け、ぐにゃぐにゃのアメのようになり、これまた歩行者にとって災難のもとともなりかねないのだった。かかとの高いつっかけなどはいて気楽に歩こうものなら、ところどころ柔弱となった部分にそれを取られ、ましてやたいそう痛い思いまでする始末。そんな頭の痛くなるような舗装の目抜き通りだったのだけれど、それでも雨が降ればぬかる道になるそこいらの生活道路と比べたら、文化のにおいがする快適な代物なのだった。ぼくにとっては通りすぎる自動車が残して行く排気ガスまでもがなんとなくかぐわしく、心地よい文化のにおいでもあったのだった。またガタンゴトンという騒々しい音とともに往来する路面電車も、言うならば、文化の音だったのかもしれない。
今、そういった音というのは目抜きの通りでは聞かれなくなった。その代わりに疾風のように走り抜けてゆく、高性能にパワーアップされた自動車の列。文化的といえば、これほどの文化をむかしの人たちは夢見なかったかもしれない。大きな声を掛け合う人々の声もなく、静かだけれど、それでいてむさくるしい喧騒の文化をだれがゆめみただろう。あんなだったけれど、穴ぼこだらけの道路がなぜかなつかしい。
|
343 火
04/03/31 |
|
ほのおというのには不思議な魅力というようなものがあり、人はそれにとりつかれているというようなところがあるようだ。人の生活の中で『火』はどのようなかかわりをもっているのだろう。
まず調理のために火を燃やす。風呂を沸かす。仏壇にロウソク、線香を供えるなど、人の生活に『火』を欠かすことはできない。ダイオキシンが発生するというので、最近は自宅の庭でゴミを燃やすということが少なくなったけれど、廃品回収にも出せないような紙くずや、再利用のできないダンボールにちょっと火をつけて燃やしてしまおうとはじめてしまうのが『焚き火』。あるいはまた正月を迎えるにあたり、大晦日などに神社などでも大掛かりな焚き火をしたりする。宗教の儀式にも『炎』は欠かせないアイテムといえる。キャンプなどでは、飯ごう炊さんだキャンプファイアーだ、などといってこれまた火を燃やす。夏なぞ、そしてお祭り騒ぎともなる。
豪快なキャンプファイアーを囲んで歌ったり踊ったりが終わったあとも、あちこちから燃えそうな木切れを探してきては小さな炎を囲んで、何が話し足りないのか何人かが居残っては夏の終わりの気配のする広場でとりとめもなく語り続けたりする。キャンプの醍醐味はこれにあり、という方もいるかもしれない。これは不思議なのだけれど、ぱちぱち燃える炎を囲むと、とんでもなく荒唐無稽な話しや、怖い話だの・・。とにかくどうしてあんな話を長々としたんだろうと、翌朝の飯ごう炊さんをしながら眠い目をこすったりする始末。
あるいは今でこそそういうことはなくなってきたけれど、冬なぞ、秋にため込んでおいた焚き木や薪を細かくしては、囲炉裏や暖炉、ストーブなどで『暖』をとるために燃やす。絶やすことなく延々と燃やす。
囲炉裏などでは、客人とその家人が火を囲みながら、食事をし、酒を飲み、暖をとりながら、尽きない話に時を過ごす。そんな夜にも、話はとりとめもなく続き、「なんとかはやっぱりいいね」とか「ほんとうによかった」などと深く納得してしまいながら、互いの親交というか、その人と人とのつながりのかくもすばらしきかななどと。
ぼくはタバコはやらないけれど、むかし吸っていた頃を思い起こしてみれば、やはりそれとの付き合いは『火』であったようなきがする。タバコを楽しむとは、やはり煙とともに火がそこに燃えるからではないかしら。
人類がはじめて火と出会ったとき、それはまさに神秘的で恐ろしいものだったはず。おそらく最初の火との出会いは、自然発火で起こった山火事かなにか。そして火への恐れを克服して自分の道具としたとき、『文明』ということばが生まれたのかもしれない。とにかくそのときから火は恐れの対象から、心の安堵、平安へと変化した。
火とはいったい何なのかと疑問に思ったら、実際に焚き木に火をつけてそれを見つめてみれば以外に簡単に答えを導き出せるかも知れない。その炎を見つめるにつけ、形もなく、実態も定かでなく、赤く、熱くゆらめき、神秘的。そしてどこかに恐れを秘めている。それにしてもやはり『火』とは、理解を超えた不思議な存在なのです。
|
344 節 約
04/03/31 |
|
春も立春をすぎ、桜の季節ともなってくると、潮干狩りのアサリ採りの時期。魅惑の干潟で熊手をガラガラやった結果、満足な収穫があったとしてそれを家に持ち帰り、潮水で砂を吐かせ、待望の料理、食卓。
楽しみなのはそのアサリを食べたあと。これはまったく理解に苦しむところなのだけれど、どのご家庭でも召し上がったあとのアサリの残渣、つまり貝殻。
まずおおかたの主婦は決まってこの貝殻をゴミと一緒に出してしまったりはしない。十中八九の主婦はこの貝殻を『道普請』に使う。それも自分の屋敷内のどこか。たとえば軒の雨水の滴り落ちて水溜りのところとか、すこしでも家庭菜園でもあればその通路など。そういったところに掘って採って来て食べた残りの貝殻を大切に撒く、というよりは入れる。そしてしっかりと足で踏んで粉砕をする。そのときのジャリっと貝殻の割れる音のなんと心地よきかな、というのが主婦としての小さな至福とでもいうのでありましょうか。 『道普請』といえば、茶碗などの瀬戸欠けなどもその材料として供されるアイテムといえる。
おそらくは雨水の浸水でつっかけ履の足がぬれないように、流亡した土を補うのが目的なのでありましょうが、それならば砂や砂利をいれるなりすれば事足りる気もする。そういえば庭から出土した小石なぞも敷地内の陥没している部分に丹念に置かれたりする。アサリ、瀬戸欠け、小石。どうやら同様の目的で普請に供されるのかもしれない。考えてみれば、土と比べて流亡しにくいし、それ自体ぬかるむ素材ではない。
タマゴ料理でふたつに割ったタマゴの殻なぞも、無駄に捨てられない貴重な資源であったりもするようだ。丹精込めている花壇や植木鉢などに、タマゴの殻を伏せて置く。土壌への有機質とカルシウムの補給というのが目的なのかもしれないけれど、これもまたよく見かける風景といえる。
貴重な生活物資のリサイクルという点で家庭の中にも目を転じてみるならば、買物の包みをしばっている『輪ゴム』などもおいそれと捨てられないアイテム。そのうち使うだろうと、引き出しのぽっちだの、腰掛の背もたれの出っ張りなどに輪ゴムをかけておく。これも需要と供給のバランスが大きく崩れているため、たまってゆくばかりとなる。そのうち、どの輪ゴムも性が抜けてしまい、役にも立たなくなり無様(ぶざま)な風景となる。
裏が白紙の広告を刻んでつくったメモ用紙のたば。マヨネーズやペットボトルのふた。ヨーグルトやプリンについていたプラスチックのスプーン。まだ使えそうなポリ袋、スーパー袋。
主婦というか人間のけなげとも言うべきこの行いというのは、ほかならぬ『節約』という精神に深く根ざしているのではないかしら。些細といえば些細だけれど、世の中の人々のそういった精神というか心がはたらいて行われる数々の事柄。実にすばらしいのかもしれない。ぼくも弁当などについてくる割り箸なぞ、もったいなくて使わずにとっておく。たまりたまって、そのうち使わずにゴミ箱行きなのだけれど。我が身のかくもいじらしきかな。
|
345 カルタヘナ議定書とGM作付け
04/04/16 |
|
遺伝子組み換え作物、作付けの動き
昨年9月、世界で50番目の国パラオがカルタヘナ議定書に調印しました。規定によりその90日後から、この議定書は調印国間で効力を発揮するようになりました。日本は昨年11/21、議定書に調印。準備のための90日を猶予期間に、今年の2/19から議定書の内容が発効するようになりました。
その影響で今、新たな問題点が浮上してきています。
まず前置きとして
地球の環境についての国際的な会議として、『地球サミット』というのがあります。そのためにふたつの条約が作られています。一つが地球温暖化問題に対するもので『気象変動枠組条約』、もう一つが地球の生物の種の保護を目的とした『生物多様性条約』という国際的な条約が作られています。
さらに気象変動枠組条約の中で、温室効果ガスの排出を減らすための『京都議定書』が1997年に採択されています。そして生物多様性の保全を目的として、『カルタヘナ議定書』が南米ブラジルのカルタヘナで1992年に採択されました。
カルタヘナ議定書は50カ国の参加があってはじめて効力を発するという規定がありました。長い年月を要してやっとのことでカルタヘナ議定書が日の目を見たことになります。しかしながら、世界で遺伝子組み換え作物の栽培を推進している米国、アルゼンチン、カナダの批准はまだありません。
そんな状況の中で、今回次のような3種の遺伝子組み換え(GM)作物の第一種使用規定(一般の開放されたほ場での栽培のこと)に基づく栽培認可のための申請が農水省に対して提出されました。
1 | 青紫色カーネーション | サントリー |
2 | チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MON810) | 日本モンサント |
3 | コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MON863) | 日本モンサント |

GMカーネーション。今までは国外で栽培したものを輸入していました。 |
これらのGM作物についてはすでに、一般ほ場での栽培認可が降りていますが、実際にはそれぞれの企業の実験ほ場だけでの試験栽培にとどめられていました。このことはすでに栽培認可が降りているにもかかわらず、ちょっと理解しにくく矛盾があるようにも感じられますが、これは実は次のような理由によるものでした。
カルタヘナ議定書の条文の中で次のような規定がなされています。遺伝子組み換え作物を第1次使用(一般の環境で栽培)することで自然界に放出する場合には生物の多様性を保全するため、そのリスクを規制、管理、制御するための措置をとるよう、調印国に求めています。 |
日本がカルタヘナ議定書に調印する以前には、そういった『規制、管理、制御』といった措置のための具体的なガイドラインがなかったため、一部の推進派によるGM大豆の作付けが人目を忍んで行われていました。その事実が発覚した時点で、県やJAなどが大事をとって処分をさせてきたという経過があります。もちろんモンサントの除草剤耐性大豆は食品としても栽培目的にも認可が降りているので、日本で栽培するのは自由だったわけです。しかしそれによる未知の環境被害、風評による経済的被害などの危険を避けるため、作付けされたGM大豆の処分を指導したというわけです。
昨年7月には茨城県谷和原村で、作付けられたGM大豆が開花。処分の要求が応じられなかったため、民間による強制鋤き込みが行われ、刑事事件にも発展しています。
カルタヘナ議定書は発効したけれど
現在カルタヘナ議定書には、現在80カ国以上が批准している。にもかかわらずこの議定書にも京都議定書にも、環境に大きく負荷を与えている米国の批准への動きはまったくありません。
また議定書が日本で発効したおかげで、具体的なガイドラインが作られたわけですが、反面、届け出をしてガイドラインさえ守ればGM作物を栽培してもよいことになる。これはある意味、推進派にとっては合法的手段が可能となったことにもなります。
GM作物は米国にとって経済戦略の一環
GM推進国の政治力を背景にしたGM作物の作付けへの動きは、いずれは日本もGM汚染させてしまえば、仕方なくGMを受け入れるだろうというもくろみも含まれているといわざるを得ないのです。
そんな状況に対して、現在日本各地でGM作物の作付けを拒否したり、国に対して意見書を出したりする動きが、北海道、茨城県、神奈川県、滋賀県などの自治体から出ています。農業をメインにしている地域にとっては苦肉の策ともいえます。
今後、ガイドラインはあっても、GM作物の作付けはさせないという明確な意思表示が各地でされるというのが防衛作ともなるでしょう。
ここで明記しておかなくてはならないのは、こうした地方行政の動きは、とりもなおさず消費者の「GM食品はいらない」という意識が原動力となっているのだ、ということです。ですから今後、地方行政、生産者、消費者などがお互い敵対しあうことなく提携しあってゆくことも、GMを含めて食の安全を守ってゆく重要な決め手となってゆくものと確信します。
生産者と提携し、自分たちの団体の中だけでも『食』の安全を享受してゆけばとりあえず健康は保たれる。という考えもあるのかもしれません。しかしながら、それだけでは問題の解決にはつながりにくい。取り返しがつかないとまで言われる環境問題は、すでにわたしたちの生活、健康の領域にまで迫っているわけです。
今後、環境の問題は、その地域全体で取り組んでゆかなければ決して解決されるものではありません。
とりあえず自分の意思表示として、GM食品は買わない!というのが第一歩だと考えます。
|
 |
346 フクロウ
04/04/15 |
|
ぼくらが子供のころ、勉強のために必要な電気スタンドといえば、白熱電灯に笠を被せたものが多かった。ちょっとよくできたものだと、夜中の枕元をうっすら燈す小丸電球が付いていた。そして小さな明かりがむき出しにならないように、ガラス製のカバーがしてあった。そのカバーの形がフクロウだったりしたものだった。
おそらく、そんな電気スタンドを覚えているという方は、年の頃ならもう50歳を越えていらっしゃること間違いなし。
その他気付いてみれば、ふくろうのキャラクターの利用されている小物類は意外と多いもの。
日本ではこのふくろうは『福籠』『不苦労』『富来労』などと当て字をするそうで、いずれも縁起のよい動物として考えられています。
古代メキシコでは
地底の世界、つまりあの世と現世を結ぶ使者として考えられていた。または『富』の象徴。
古代マヤでは
豊穣と死の両面を兼ねる鳥として、やはり畏敬の念を持って崇められていた。
古代ギリシャでは
ローマ神話の学問・知識と工芸の神『ミネルバ』の従者とされていた。
|
 森の賢者というにふさわしい風貌
森の賢者というにふさわしい風貌 |
中国では「悪魔祓いの鳥」、オーストラリアの原住民アボリジニは守護神として、またアイヌ民族には守護神『コタンコロカムイ』として。要するに、世界中でこのフクロウという鳥は畏敬の念を持って、あがめられてきたといえるでしょう。そしてけっこう身近な存在でもあった。
なぜなんだろう。と不思議がる前に、当のフクロウをじっくり観察してみれば(実際はそんな機会はめったにないけれど)、そんな疑問はどこかへ消えてしまうことでしょう。
扁平な顔に大きな目がならび、可愛い口(実はそうではないのですが)があって、どう見ても鳥の顔とは思えない。そして、その表情は深く何かを考えている賢者を連想させるところがある。というわけで、世界中でこのフクロウという鳥は、一種何かの守り神のような存在で、アンタッチャブルなものなのです。
ぼくも子供のころ、神社の近くを夜通ると決まってふくろうが「ホー、ホー」と鳴くのを聴いたもの。そして一度だけ見たこともあった。
フクロウとは別にミミズクという種類がありますが、コノハズク、アオバズクなどのように『ズク』と付くのがミミズクで、一般に耳のような羽根の出っ張りが頭にあるのがミミズクの特徴だそうです。ただし例外もあって、北海道の『シマフクロウ』には耳のような突起があります。 |

シマフクロウ |

コノハズク |
そんなフクロウ、ミミズクは今日本からどんどん姿を消している。その理由はまず人間の開発。肉食の鳥に似合わず、フクロウが俊敏さに欠けること。群れをなして生活する鳥ではなくある範囲のテリトリーを持つため個体数が少なく、何らかの原因でそれが失われた場合、用意に補充されない。
音羽町のもっと奥山に鳳来町というところがあります。道長の梅の産地でもある鳳来町といえば、「ブッポーソー」と鳴く『コノハズク』でよく知られています。コノハズクは愛知県の県の鳥となっていますが、深刻なことにこのコノハズクもレッドデータブックに載せられていて、絶滅寸前種とのこと。
かつては、ちょっとした森や林のある神社などにも必ず一羽はいたミミズク、フクロウなのだけれど、今では住むところを追われ、伝説やキャラクターとしてだけの鳥となってしまいました。 |
|
いうなれば、人里からそんなにはなれていなくても、ちょっとした環境さえあれば住んでいた鳥。ある意味で、わたしたちの心のよりどころともいえた鳥が、フクロウ、ミミズクだったのです。 |
 |
347 バートンフィンク
04/04/24 |
|
以前にも観たことのある『バートンフィンク』という映画のビデオを観た。これはユニークな映画を手がけることで評判なコーエン兄弟(米国)によるもの。この映画の他に『ファーゴ』『ビッグリボウスキー』など。
この映画については、肝心な部分について話してしまうとちょっとまずいのでそれはやめておくとして。時代は太平洋戦争直前。ある新鋭の人気演劇作家バートン・フィンクがその可能性を買われ、ハリウッドの映画会社に雇われる。そこでなんとどうでもいいような二流レスリング映画(よくあるヒーロー物のような)の脚本を書けといわれる。安ホテルにタイプライターを持ち込みとう留し書き始めようとするのだけれど、そんな映画の脚本なぞ書く気も起こらず、最初の数行で後がさっぱり続いてゆかない。
季節は暑い夏で、ホテルがまるごとオーブンになったよう。彼の部屋には扇風機こそあるのだけれど、風も通らずただ暑い。滅入るような雰囲気の薄暗い部屋。その隣室には太った保険のセールスマンが泊り込んでいる。フィンクは「人の苦しみを取り除いてやるのが自分の仕事」だと話す彼とは妙に打ち解けあえるのだった。
古臭い柄の部屋の壁紙は、それを貼付けてあるニカワが暑さでとろけ、流れ、角のほうからベロンと剥がれだす始末。そのホテルでフィンクはやはり映画会社に雇われている今では酒におぼれ、落ちぶれてしまったかつての名作家とその恋人に出会う。なんとフィンクの尊敬するその作家の作品の一部はその女性が書いていたのだということを知り、彼はすっかり幻滅してしまうのだった。筆が進まず困り果てたフィンクは、脚本のヒントをもらいたくて彼女を部屋に呼ぶのだけれど、結果として情事ということになってしまう。
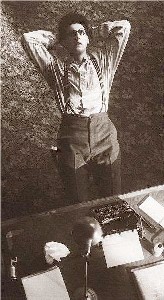
|
どれだけの時間が経過したのだろう。そんなはずはないのだけれど、目覚めた彼の傍らに横たわっていたのはなんと、ショットガンで胸をえぐられた血まみれの女の死体だったのだ。しかも死後間もない。
無実の確信はあるのだけれど、恐ろしくてまずは隣室の太った男を呼ぶのだった。以外にも男はその死体を処分してしまう。そしてしばらくしたらまた帰ると言い残し、男は仕事のため出かけていってしまう。そのときわけのわからない包みを貰い受けるのだけれど、どうやらその中にはとんでもないものが・・。なんとその男は連続猟奇殺人犯で、幾日か経ってやってきた刑事にフィンクは血まみれのベッドを証拠に、殺人の共犯者ということにされてしまう。そこに太った男が帰ってくるのだけれど、その時にはすでに男が放った火がホテルを包み始めているのだった。居合わせた二人の刑事はショットガンで殺され、犯人の男も炎の中で死を選ぶ。
ここまでの悪夢というか、現実というか虚構というか。とにかく映画は現実ではないのだけれど、そのあらすじ自体が現実なのかどうなのか。それが夏の暑さと火事の熱さでわけのわからないものとなる。
実はこのあらすじなぞまったくどうでもよくなってしまうような衝撃的なラストシーンで映画は終わる。それは予測もつかない、鳥肌の立つもの。そこで映画はピクチャーなのだと実感するのです。 |
|
 |
348 河田昌東さん退職
04/04/27 |
|
河田昌東さんといえば、遺伝子組み換え、チェルノブイリ救援、反原発、四日市公害、藤原町、芦浜原発などと中部の社会運動に大きく実績を残すひと。ぼくたちは遺伝子組み換えでお世話になっている。遺伝子組み換えだけに限ったとしても、彼なくしては科学的な面からの運動の展開は無理なことといえる。
その河田先生が30余年勤めた名古屋大学をめでたく退職という運びとなり、有志の人たちにより『退職記念パーティー』が催された。一次会の茶話会(持ち寄りの豪華食材による)では100名ほどが参加。ぼくも。
ご本人はこういうのは大の苦手らしく、遺伝子組み換えについての講演を始めるときよりも硬い面持ち。そして、ご丁寧にも大学卒業以来の半生について1時間あまりも話すという趣向がもたれたのだった。彼、河田昌東がどのように社会運動と係ってきたのかというのが主な話題となる。1960年代、安保紛争を契機に起こり始めた学生運動が大学管理法を契機に全共闘時代へと進むころから、彼の話は始まってゆくのでした。
というような話となると、また硬くてあくびでもでそうなものを連想してしまいそうだけれど、そうでもなかった。反対にとてもたのしい話であったのです。三重県芦浜原発に対したのをきっかけに、芦浜で獲れた魚を名古屋まで運び、配達してまわる仕事までして5年間過ごしたとか、問題の起きている地域の土壌や水を採取してきては日がな分析なぞした研究室での日々とか。勝手に大学で私的な講座などひらいて学生に教えてみたり、この人は一体大学で何をしていたのだろうと考えてしまうほど、いろんなことをしながら社会運動に参加しての30数年。
彼いわく、「雑食性でなにかおいしそうなものがあると、つい首を突っ込んでしまう」のだそうで、いくつかの活動団体をはしごしていたりする。
そんな話の中で印象に残ることがあった。それはどの社会運動も、政治活動とは違うということ。よくよく考えてみれば、社会運動とは何かを攻撃するものではなくて、『守る』のが第一の目的なのです。この守るという行為は、これ以上は我慢できないというところから起こってくる。そしてさらには、もっと良くしたいという希望的意志がある。そういった意志を阻む権利は何人(なんぴと)にもないわけだし、それには手が差し伸べられなくてはならない。

名古屋YWCAにて(04/04/23) |
『文化』とは一般的に創造されるべきものであるのに対して、『生活』という『文化』はやはり『守る』ところからまず始まるべきだと思う。『食』の文化はまさにそうだと思う。中国の故事にある『身土不二』という言葉はまさにそれを意味する言葉だと思う。
名古屋大学の図書館の古株事務員女史が河田さんに言ったそうだ。「あんたは大学の先生では絶滅危惧種」と。それに対し祝賀会の壇上で彼はこう言ったのでした。「わたしはとっくの昔に名古屋大学を辞めていました。そして今年の4月で、ぼくは絶滅しました」と。 |
|
 |
349 田園風景
04/05/12 |
|
時も黄金週間の頃ともなると山野のみどりはもえたち、やがてそれが田畑へと移ってゆく。春4月に播かれた種からは可憐な双葉が芽吹き、やがてその作物にふさわしい形をした葉が育ち始める。
毎年のことだけれどいまどきになると、「ここは水の里だったのだ」とあらためて感激してしまう。日本の水田というのはまことに巧みにできていて、そこが平地であろうと山の傾斜地だろうと、命の水がその微妙な傾斜を利用した水路を伝って導かれてやってくる。引き込まれた水ははじめ田んぼに黒い染みを付け始め、それが広がり、やがて一面を満たす。昔とちがって今では『代掻き』はトラクターに乗ったままで気楽。それが済めば今度は田植え。これも熟練作業だけれど、田植え機があればいとも簡単。
というわけで見まわすといつの間にかあぜ道だけを残し、田んぼは青い空と緑の山を映す鏡に変身しているのでした。その鏡の水面(みなも)をよく見ると、いましたいました小さな稲の子供たちがきちんと並んで整列っ!。まだ水におぼれそうでたよりないけれど、梅雨となり、それが開けたころにはなんとたくましくなっていることでしょう。そのころには水面のさざなみは、稲の成長で緑の波に生まれ変わって里中を被うことだろう。
稲の生長のために百姓たちは何をするのだろう。春の田起しから始まり、入水、代掻き、田植え、草刈、田の草取り。そろそろ分けつが進むころ(田植えから45日過ぎたころ)中干し。補肥え・・・。と決まりきった作業のほかに、じつはこれもまた大切な作業がある。畦の草刈、モグラの穴ふさぎ、水の管理というような朝な夕なの細かな気配り。
稲作は日本の農というか、食というか、生活、文化の原点ともいえる。そしてその景観は日本の原風景といってもいいすぎではないと思う。考えてもみれば、むかしぼくらが四季を通じて体験したいろんな行事の数々は、どれも農と関係していたんじゃないかしら。その中で稲作はとくに大きな意味がある。
湿地でもない畑に水を引き入れて田んぼを作る。それが日本中で行なわれる。毎年毎年、それこそ何千年もむかしから繰り返し行なわれてきた米つくり。多少の技術の変遷こそあれ、基本的にはずっと昔から変わらない。日本人は、起伏の多い土地で、木々と一緒に暮らし、水を巧みに利用し、米を育ててきた。これはすごいことだと思う。なにがすごいかというと、もしかすると日本には手付かずの自然なぞほとんどなく、やっとのことでひとびとがそれを守ってきたおかげなんじゃないか。
外国の自然にはただ厳しいというか雄大な手付かずの風景があてはまるけれど、日本のそれにはそういった雰囲気とはちがい、どこか片隅にひとびとの生活のにおいがする。わらぶき屋根があったり、田んぼがあったり、一本杉があったり、道があったり。日本人は自然と対峙するのでなくて、ともに暮すことを選んだのだと思う。そのきっかけとは遠い縄文の、なにあろう『稲』との出会いだったのではないかしら。 |  |
|
 |
350 河合果樹園
04/05/13 |
|
愛知県豊橋市中原町、もう少し向こうはもう静岡県というところでハウスでみかんとレモンを栽培している河合浩樹さんを訪ねた。以前農業改良普及センターの起業者交流会で同席して以来気になっていて、一度お話を聞かせてほしいと思っていたため。
ここ中原町は比較的温暖な気候で果樹の栽培にも適した土質ということもあるのだけれど、静岡三ケ日や蒲郡のようなみかんの大特産地と比べるとブランド性もなく、こじんまりとした生産者が集まっている。一見不利ともいえる条件を『ハウス栽培』という技術でカバーしているのがこの中原町のかんきつ農家の特徴といえる。ハウス栽培というと、農薬や土壌消毒といった環境に負荷のかかる農業を連想しそうだけれど、方法によっては減農薬、さらには無農薬無化学肥料栽培も可能。
河合さんのレモンの育て方はユニークなものだけれど、にもかかわらずとても理にかなったもの。それにはハウス栽培のノウハウがしっかりと生かされている。まずおどろかされるのは、彼のレモンが地面に植えられていないこと。なんと『ボックス』という50リットルほどの植木鉢が使われている。収穫のためのレモンの木は、20年あまりの寿命をボックスという窮屈なところですごす。これではレモンの木がかわいそうなんじゃないかしら、と思ってしまうのはぼくだけではないらしく、見学に訪れる消費者たちも同意見とのこと。
各レモンのボックスには潅水用のノズルが差し込まれていて、細々と水が供給されている。ハウスでの健康的な環境作りは一にも二にも土作りで、河合さん自作のボカシ肥が主力。だからレモンのハウスの地面は放線菌というカビの一種で白っぽくなっている。病原菌を寄せ付けない環境もちゃんと作られているんだなと実感もする。
ハウス栽培の一番のメリットは潅水をコントロールできること。それによりレモンは根をいっぱいに張ろうとするのだけれど、ボックスで抑圧されてしまう。その分のストレスを甘く凝縮した果実のために発散させるという仕組みになっている。レモンは温暖な気候と薄日(日陰ではないが直射日光でもない)を好むため、ハウスという環境はむしろ適していると河合さんは説明してくれた。
河合果樹園では地元のいくつかの仲間と共同での出荷もしていて、農協出荷にはあまり頼ってはいない。中でもレモンについては固定客をつかんでいて今年もすでに完売。とくに年明け春にかけての完熟レモンは、色、つや、香り、酸味、さらに甘味にいたるまで絶品といえる。ぼくも河合さんの自家用のためのレモンを10Kgほど分けていただいたのだけれど、彼の言ったとおりそれにはフルーツの名がふさわしくとても美味。スライスしたそれをみんなで平らげてしまった。
河合さんはレモンを『いじめて』甘い実をたくさん採るのだと説明してくれたけれど、そのための彼のレモンに対する気配りというのは裏を返せば『愛情』以外の何ものでもないのだなとじゅうぶんに納得もした。 |

わかりにくいですが、レモンはボックス(プランター)で栽培されています

河合浩樹さん |
|
河合果樹園のHPはこちら
http://www5.ocn.ne.jp/~kawaikje/ |
 |