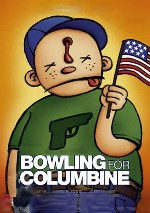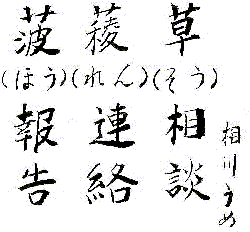|
361 新天地 04/07/28 |
||||||
|
||||||
|
362 銃と米国 04/08/05 |
||||||
|
||||||
|
363 終 戦 04/08/18 |
||||||
|
||||||
|
364 オリンピック 04/08/18 |
||||||
|
||||||
|
365 生きる 04/08/26 |
||||||
|
||||||
|
366 ともだち 04/09/01 |
||||||
|
||||||
|
367 出戻り猫 04/09/08 |
||||||
|
||||||
|
368 報連相 04/09/15 |
||||||
|
||||||
|
369 眠る男 04/09/20 |
||||||
|
||||||
|
370 青春デンデケデケデケ 04/10/02 |
||||||
|
||||||