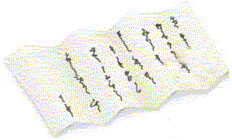401 笑の大学
05/05/18 |
 |
ビデオで『笑の大学』というのを観た。喜劇作家三谷幸喜の脚本。戦前の庶民の娯楽といえば映画、演劇。大衆演劇の主流といえばやはり喜劇で、当時エノケンこと榎本賢一率いる『笑の王国』の専属作家、菊谷栄という人をモチーフにしているそうだ。そんな昭和15年当時、太平洋戦争に突入しようとしていたご時世で、思想統制はいよいよ大衆喜劇にまで及んでいた。そんな時代の劇団『笑の大学』の専属喜劇作家、椿一(つばきはじめ)とその脚本を検閲する警視庁保安課、向坂睦男(さきさかむつお)の警視庁取調室でのやり取りがこの映画。
実は、ぼくはこの映画の元になった同名のドラマを10年以上前のNHK-FMラジオで聴いたことがある、というか録音したそれを時々今も聴いているのでした。三宅裕司(向坂)と坂東八十助(椿)が出演。検閲官のあまりの無理難題に、椿が発する「向坂さん」という台詞が印象的でおもしろい。出世魚という言葉があるけれど、このラジオドラマはさらに劇場へ、そして映画へと出世しためずらしい例。
とにかく、そのドラマが映画化されたということで興味津々。やはりというか2回の脱皮を重ねただけのことはあり、さらにおもしろく、物語としても完成され、とっても楽しい映画。とくに堅物(かたぶつ)検閲官役の役所広司がすばらしい。そして喜劇作家役の稲垣吾郎もなぜかすごくはまり役。
そもそも喜劇というような『笑い』なんぞにはまったく興味もなく、すべて上演禁止にしてしまえばいいとまで考えている検閲官にとってさえも、椿という男は骨があって出来る作家であったのだろう。持ち前の緻密な性格からか、はたまた実は潜在していたのかもしれない喜劇へのあこがれからか、検閲官向坂は椿の台本が気になって仕様がない。本来『不許可』の朱の判を押さなければならないにもかかわらず、あれやこれや訂正、削除を繰り返すうち、なんと台本はどんどんおもしろくなっていってしまうのだった。しかしながら、最後の許可を出さんとする折、気を許した椿の本音の言動で検閲官向坂の態度は一転、そして暗転・・・。
|
|
ぼくがまだちいさい頃、音の出る蓄音機とラジオは家庭での大衆娯楽のすべてといっても過言ではなかった。大切なラジオは子供の手の届かない、なるべく電波をよく受ける茶だんすの上などに置かれ、人気の番組の時間なぞにはラジオを見上げつつ真剣に聴いたもの。そのラジオに大衆が求めたものはなんだろう。それはテレビが主役になった今も同じこと、『笑い』。笑いのための、いかにも愚かしいネタにさえ、でもそんなものでもなんとけなげにも、大衆はただおかしいというだけで笑い、それだけで幸せな気持ちになってしまうことができる。いや、そうではなくて、ささやかな笑いをもってしてさえ、せめて刹那でもいいから楽しく笑いたいのかもしれない。
検閲官向坂は椿に「笑いのない台本にしろ」と最後通牒を突きつける。笑いのない喜劇とは、笑いのない生活、笑いのない人生につながるのかもしれない。笑いというのがささやかな幸せだとすると、笑いのない人生とはなんと悲しくさびしいものなのだろう。『笑い』。ぼくも今ここで心から笑いたいと願っている。 |
|
 |
402 ラヴレター
05/05/25 |
|
ぼくも若かりしころ、ラヴレター(恋文)というのを書いたことがある。そしてこの文をお読みの方々も、一度や二度、三度四度、恋文をしたためた経験がお有りではなかろうか。年月が過ぎ、家庭を持つようになった今になって思い出そうとすると、恋文とはなんとくすぐったいというか、恥ずかしいというか、もし今も残っているとしたら、絶対に見返したくないものなのかもしれない。
ある人にはじめて出会い、あるいは日常顔をあわせていながらある日突然その人が気になる存在になってしまったとする。すると人は気持ちのどこかに平常とはちがう、要するに異常をきたしてしまうことになる。それをずっと仕舞っておく場合もある。いわゆる片思いということになるのだけれど、そんな気持ちも時の経過とともにどういうわけか増幅されてゆき、胸の中に蓄積されてゆき、次第に質量ともに大きくなり、とうとう持ちきれなくて限界ということにあいなる。そんなころになると、もう言葉で「すきです」などと相手の前で吐露する気力というか勇気もなくなり、あとは恋文でといういことになる。
まことにけなげというか、あるいは哀れというのか、夜も更けるころ、ひっそりと恋文をということになる。あるいはここで携帯でメールということもあるのだろうけれど、とにかくその段となるとけっこう大胆な言葉も飛出し、とんでもない内容のものができあがったりするもの。時も満月だったりして、とにかく狂気にも似た心のうちが恋文という文章のなかにいかんなく発揮され、記されることになる。「ままよ」と恋文は相手の靴箱又は発信ボタン。
さて、そんな恋文が届いたとして、はじめてそれを受け取る相手はどんななのでしょう。実は残念ながらぼくは恋文を最初に書いたことはあっても、はじめて受け取った経験がないのでした。そこのところがなんとも残念というのか、悲しいところ。おそらくは受け取ったとき、うれしいのかしら。実際にそれが『意中の人』からのものなら、それもそうなのだろうけれど、そうでない場合には戸惑ってしまったり、あるいは嫌悪感さえおぼえる相手からなら、どう断ってしまおうかこれもまた苦慮するところ。それともまったく見ず知らずの人からの恋文であったならば、今度は期待に胸膨らむといったところなのだろうか。
これで受け取った本人は恋文に対する『返信』をということになる。「わたしもあなたがすきでした」などという内容の恋文を返すという場合、やはりこれも夜の帳が降りてからということになるのだろう。最初に書いた本人のものと比べると若干冷静に、そして選びぬいた一語一語で返すということになるのだろうか。
|
こんな風に「すきです」「わたしも」というようなやり取りが夜な夜な行なわれる。傍から見たり、年月経ってから思い起こしたりすると、なんともどうかしている、どうかしていたというようなものであるのかもしれない。
けれど、人というのはそんないわば、躊躇なくすべてをさらけ出すというようなこともなくてはいけないのかもしれません。独り言でもいいからそんなことしたとすると、自分もちょっとはおとなになれるのかしらん。 |
|
 |
403 米の文化
05/06/07 |
|
今年も稲の季節がやってきた。大雨や寒風でも吹き荒れればいっぺんでちじみあがってしまいそうな幼い苗が、初夏の涼風にそよそよとゆれている。もう少し大きくなれば風を受け、目には見えないそのかたちをすばやい稲の波であらわすようになるのだろう。緑の稲。まったく美しいと思う。
緑の波、水の国、日本、アジア。米を主食にする人たちが住んでいる。初夏や雨季ともなってくると一気に農家は活気付き、直播やら田植えやらでいそがしくなる。あれだけ殺伐としていた場所に水が引き入れられ、水田となり、稲が作付けられると、あたり一面が緑のじゅうたんをひきつめたような生命感あふれる世界へと一変する。
この国はこんなにも豊かなところだったのかと、人々ばかりでなく、すべての生物たちがそこに生まれたよろこびをあらためてかみしめる。
そんな国で、そんな季節に『稲』を手掛けると、人はそれを手塩に掛けて育てるという気持ちになってしまうものなのかしら。稲は水がいのち。だから人は己の水田の水が気になる。我田引水とばかりに、他の水田の水をこちらに無理矢理引いてさえ、自分の稲のことが気になってしようがない。畦はモグラに穴を開けられていないか、そろそろ恵みの雨がほしい。雨が降れば降ったで今度は病気が気になり、イモチだ、やれカメムシだ、台風だ、豪雨だ、分けつだ、出穂だと一喜一憂の日々ということになる。それほどに米文化の『稲』を手掛ける人たちにとっては、米作りは子育てのように手のかかる仕事。
そして収穫、脱穀、乾燥、籾摺り、精米、そして食卓。ここでもまたたっぷりの水を使って炊きあげる。これがまたなんともうまい。米とはまさに『主食』の名にふさわしい作物だと感心してしまう。
多くの米文化の国々の日常の食事の主役はやはり『米』。これは大げさでもなんでもなく、他のおかずは主食である『ごはん』をおいしくいただくための添え物とさえ位置づけることもできる。
米文化に欠かせないのが『発酵食品』。みそ、みりん、納豆などなど。たとえ大豆や麦の糀を使うみそだろうと醤油だろうと、ほとんどの発酵食品のための糀を育てるには『米つぶ』がなければならない。それほどに米文化の国々にとって『米』の存在は大きく尊い。
|
世界のあと半分には『麦』の文化がある。麦は少ない雨でも、他の雑草に負けることなく元気に育つ。麦を手掛ける人たちにとって、麦はいかに手広く、合理的に育て、収穫するかがおおきな感心事なのかもしれない。
彼らにとって、もちろん麦は主食であるにはちがいない。けれども米を主食にする民族とくらべると、その意識はちょっと薄れるのかもしれない。ぼくらが『米』を米として食べるのに対し、彼らはそれを加工して食べる。これには大きな違いがあるような気がする。そのぶんだけ、食と農とのより強いかかわりが、『米文化』としてぼくらにはあるような気がする。だからこそぼくたちは『米の文化』を大切に守ってゆかなければならないと思う。 |
|
 |
404 修学旅行
05/06/08 |
|
ぼくは昭和26年生まれ。太平洋戦争で敗戦し、散々な兵役の後、復員で命からがら日本に帰国した男たちとそれを待ちわびた女たちの心が綾なした数々のめくるめく物語の結果、世の中は一気に生まれ育った子供たちであふれかえっていたのだった。
ぼくの姉はぼくより3つ年上。彼女たちの年代はすさまじいベビーラッシュで、中学校などでも1学年が10クラス、そして1クラスが50人以上という混雑振り。父兄の授業参観などはもうたいへんで、親たちは教室に入る隙間すらなく、廊下から開け放たれた窓越しにのぞくという始末。ぼくらの年になって少し楽になり、中学の1学年が8クラスで1クラスが42名ほどだった記憶がある。
そんな『戦後のどさくさ』だったため、ぼくらが通っていた小学校もけっこうごたごたしていた。『洟垂れ小僧』という言葉があるけれど、文字通りそんな子供がけっこういて(花粉症ではなく)蓄膿症で絶え間なく湧き出る青っ洟で、ふたつの鼻の穴からは乾いた鼻汁で白く縁取られた二本の水路が出来上がっているという具合だった。
冬に着せてもらう黒の学生服なぞ、洗濯の換えなぞあるはずもなく、肘や膝は継ぎはぎだらけ。にもかかわらず、大好きな学生服だから子供たちはそれでもよろこんで着ていたもの。しょっちゅう鼻汁を拭っているものだから、子供たちの学生服の黒の袖口は乾燥したそれで見事にテカッていたものだった。
ほんのひとにぎりの家庭を除いて世の中全体が貧乏だったからか、継ぎはぎだらけの洗濯もそこそこの服を着ていようが、青っ洟を垂らしていようが、運動靴に穴が開いていようが、銭湯へもたまにしか行けずで垢だらけだろうが、子供たちはたくましくもけなげに生きていたものだった。
そんな日本の子供たちだったから、ちょっとやそっとの家庭の事情なぞには一向にめげることもなかったのだった。そんなだったのだけれど、このときばかりはみじめな思いをしたのではないかしら。そんなことだけはあってほしくないという学校側の配慮で、修学旅行の一年前から積み立てまでをし、その旅費をなんとか確保してやりたい。学友をひとりも欠かすことなく行かせてやりたい。そんな待ちに待つ修学旅行だったけれど、それでもやっぱり行けない子供がいるのだった。夢いっぱいで出発するバスの中でその事は子供たちの間で評判にあがってしまい、その一瞬の黙祷(もくとう)にも似た沈黙に、わびしくもため息が漏れるのだった。でもそれはそれ、それ以上のことは考えることもない子供たちの心は、二泊三日の旅先に馳せる期待で胸がいっぱいなのだった。
出発の何日か前に配られた『修学旅行のしおり』だったか『心得』だったかにガリ版印刷で書いてある、事細かな「してはいけないの例」なぞどこ吹く風。やはりその小冊子に載せられている唱歌の数々の中から誰が歌い始めるのか、その中の一曲がおごそかに流れ出す。あとは堰を切ったように歌声は高らかに車中に響き渡り、その行く先でことさら感動的なものが待っているわけではないのだけれど、旅の気分は一気に高揚するのだった。
いちばんわくわくしたのは旅館を出ての夜の買物。居並ぶみやげ物店を限度額500円の予算で物色。家族に、はたまたお向いやお隣のご近所にまで気を使うというけなげさ。生姜糖やお越し、赤や青の織糸の紐の付いた、後ろからたたくとひょこっと目の飛び出る『般若の面』(おしゃれにズボンのベルトに付ける)やら、反対側に肩たたきの軟球のボールが付いた『孫の手』、学校に帰り着くまで先生に取り上げになってしまう『木刀』、ミニチュアのガラスケースに入った黄金の『金閣寺』などなど。あとで「どうしてこんなものを買ったのだろう」と首をかしげたくなるようなおみやげばかりだったけれど、乏しい小遣いから自分のおみやげもちゃんと確保しているのだった。消費税こそなかったけれど、どの子供もぴったり500円の買物を、繰り返しの足し算引き算の末、ちゃんとこなすのだった。
修学旅行の買物は、もしかするとぼくの一生のうちでいちばん胸ときめき、うれしくたのしい買物だったのではなかろうかと思い起こす。
確か学級のひとりひとりから何円づつだったか集められたお金で、修学旅行に行けなかった子供にもおみやげが買われたと記憶している。 |
 |
405 外来生物法
05/06/15 |
|
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、略して『外来生物法』というのが今年6/1から施行されたとのこと。海外から移入したブラックバスやアライグマほかの動植物20種が、この法律に登録されているそうだ。この法律の施行にあたって、とくにバス釣りファンから反対の声明、署名などが行なわれて問題にもなった。日本中のあらゆる水域で、今や駆除するどころか阻止することすらむつかしい状況のブラックバス。生態系に及ぼしている被害は計り知れないものがあろうというもの。
こういった侵略的な外来生物による被害を予防するため、環境省では『外来生物被害予防三原則』というのを呼びかけている。1.外来生物をむやみに日本に『入れない』 2.野外に『捨てない』 3.野外にすでにいる外来生物は他地域に『拡げない』というのがそれ。
この法律に違反した場合は、個人では懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金。法人では5千万円以下の罰金とのことだけれど、実際にこの法律で罰せられるか、起訴された例はまだない。現実的にこの法律の効力については、はなはだ不安を感じてしまうのはぼくだけではないと思う。
先日、近くの農業用水路でかなり大きなカメを見つけた。甲羅の長さは20cm以上はあり、なかなかの貫禄がある。とはいっても情けなくもそれは『ミドリガメ(ミシシッピーアカミミガメ)』であったのだった。在来のカメにくらべ模様も色彩的にもきれいなのはいいけれど、今このカメも日本のあらゆる池などでまちがいなくその勢力を拡大しつつある。人の集まる公園の池などで、このミドリガメが他のドロガメなどを足蹴(あしげ)に、客のばらまく『コイのえさ』を我先にとばかり群がるのを見るにつけ、このカメがいずれ外来生物法にリストアップされるのかもしれないなと思う次第。
雄なのか雌なのか知らないけれど、人間に捕まってしまったという表情なぞ微塵(みじん)も見せず、甲羅から半分顔を出し、薄目を開けてこちらを見ながら、「オレが悪いんじゃあねえ」などと言わんばかりの迫力に、なかばあきれてしまったほど。
|
このままこのミドリガメを放ってもまずい気もして、動物愛護教会に問い合わせてみた。電話に出た担当者は、教会の近くの水路にもミドリガメがいっぱいでどうしようもありません、とのこと。殺してしまうわけにもゆかないし、仕方なくまたすぐ近くの池に放流してしまったのでした。
飼ったはじめは『銭亀』みたいに可愛く、さほども大きくなるとは思えなかったであろうミドリガメ。自分から逃げ出したのか、はたまた持て余して捨てられたのかわからないけれど、なんとなく人間の『恥』をその輝くマナコに垣間見る気さえするのだった。外来生物には罪はないけれど、自然界でのその横暴ともいえる立ち振る舞いを想像するにつけ、「今畜生、このやろう」と思ってしまうのはぼくだけではないはずだ。 |
|
 |
406 汽車の旅
05/06/25 |
|
今では蒸気機関車(SL)といえばまさに過去の遺物ともいえる代物。黒煙をもうもうと吐き、蒸気が吐き出されるシュッ、シュという耳をもつんざくような音を聞くにつけ、その勇ましさといったらなかった。
とはいってもぼくの年代ではほんの幼少のころ、東海道本線をSLで東京だったか、横浜だったかに旅行に連れて行ってもらった記憶の中にただ一度だけあるくらい。それほどなじみの薄い存在なのだけれど、なぜかSLに先導されての汽車の旅はいまだに印象深い想い出として残っている。おそらくぼくが小学一年生かそれ以前のことだったのだろう。ぼくの母の生まれ故郷が横浜ということもあり、また都会への憧れもあってか、いにしえのご近所さまを頼っての旅であったと記憶している。年代でいえば、1950年代後半ということになるのだろうか。
当時の花形電気機関車『EF58型』をもってしても、愛知県岡崎から横浜までは裕に6~7時間はかかった。岡崎を何時ごろの列車に乗ったのかどうなのかはっきり覚えていないけれど、はたまたSLには途中から乗り換えたのかどうかもわからないのだけれど、とにかく『静岡駅』あたりでちょうどお昼だったような気がする。静岡といえば日本一の富士山は見えるし、おなかが減るしということで『駅弁』ということになるのだった。当時はまだ『釜飯弁当』などはなかったので、『幕の内弁当』と別売りの陶器製の土瓶と湯のみがセットになって針金の取っ手のついた、静岡名産あったかーい『お茶』を買えば、もう汽車の旅気分は上々といったところ。
制服を着た名物駅弁売り師はといえば、首から紐で吊った箱に駅弁を満載し、その箱の脇にはつり銭用の百円札を長く立て折りにして何枚もはさんでいるのだった(限られた停車時間にしかもできる限りたくさんの客を相手にするための工夫)。その売り声はちょうど浪花節師のようにつぶれてはいるものの、遠くまでよく通る声だった。
上りのその列車は左側の客席ばかりが満員で、駿河湾の広い海の見える右側の席はなぜか空いているのだった。それもそのはず、左の客席からは大パノラマ『富士山』。これもまた誰からともなく「富士が見えた」という声がかかり、反対側の座席にいる乗客もいっせいに左の車窓に目を向ける。さらに楽しみなのは長い長い『丹那トンネル』。父親の左手の腕時計を頼りに計ってみると、確か7分ほどの暗闇だったような気がする。そうそう、その日の列車は蒸気機関車だったから、誰ともなく「トンネルだぞー」の号令に窓際の者は急いで窓を閉めるのでした。

EF58型機関車 |
駅弁、日本晴れ、富士山、海、茶畑、鉄橋・・・なぞとすばらしい景色と軽快なレールに車輪があたる音、汽笛、全開の窓からは香る風。窓から首を出して進行方向を望めば、たくましくも勇ましい蒸気機関車。そんな汽車の旅に、子供たちの口からはやっぱりこの歌、唱歌『汽車』。今は山中今は浜/今は鉄橋渡るぞと・・・、大きな声で歌っても喧騒のおかげだろうか、だれも文句を言うものもいなかった。
そんな風情の詰まったあのころの汽車の旅。ひかりだのぞみだと、あっという間に東京、大阪、博多の昨今の旅とくらべると気の遠くなるほどのんびりとした旅だけれど、『夢』と『希望』だけは、今と比べたらきっと何倍も大きく、ちょうど全開の車窓から望む特大サイズのパノラマ『富士山』の様にでっかかったのかもしれない。 |
|
 |
407 雨のうわさ
05/06/29 |
|
雨が降る、降らないでよろこぶ、よろこばないという話となると、それぞれの立場によってちがってくるというもの。
雨が降って困るというのは行楽地。海水浴場、遊園地。ひと昔前までは、ドームのなかった野球場。夏の夜の試合。試合の有無を判断しなくてはならない夕方の雨模様。もっと困るのは、試合開始間もないころ振り出す雨。
遠足を明日に控えた子供たちにとって、目先の唯一の心配といえば明日の天気。かと思えば、大運動会を控えての天気はといえば、降ってほしくない子もいれば、そうでない子もいる(ぼくなぞ「降ってほしい」の部類)。その運動会のバザーの係りとなる父兄にとっても心配なところ。少々の雨でもやっつけてしまいたいというのが本音なところ。春の花見。これも満開のころ降られてしまうと、翌日雨上がりで西風がぴゅー。ただし飲ン兵衛には、桜の花びらが枝にくっ付いていようがどうであろうが関係もなし。
かと思えば雨傘屋ともなれば、梅雨時、雨が降ってくれないと商売にならない。また梅雨時でなくても、今日は降りそうもなかった日のにわか雨なぞ、傘屋にとってはにんまりといったところ。
むかしの米国映画『雨に唄えば』で、傘もささずに楽しげに踊るジーン・ケリーに「雨ってたのしいっ」。土砂降りの雨の中、哀れな捨て猫、オードリー・ヘップバーンとジョージ・ペパードのハッピーエンド。
とはいえ、雨が降っていちばんよろこぶのは誰あろう、お百姓さんでした。初夏を前に田植えした稲もひざのあたりまで育ってきたちょうど梅雨時。そろそろ補肥えをまこうかというころ、なんと今年は空梅雨。天気予報の雨印に期待を寄せるもほんのお印(しるし)程度。人と合うたびうわさは雨のことばかり。彼らの最前線『田んぼ』では、ゆるやかに、密かに、しかし熾烈に『我田引水』の水取り合戦。その駆け引きが、けっこう良い米を作るためのカギだったりもするからたまらない。
かといえば、雨が降りすぎても困ってしまうのも誰あろう、お百姓さん。ふだん水の便のよかった自慢の田んぼが一転して水没。つい昨日まで雨を待ち望んでいたのに、今はひたすら雨をうらやむばかりのお百姓さん。麦刈り前の雨をうらやむのもお百姓さん。大豆の種まきも・・・。
 |
まったく、雨に振り回されどおしのお百姓さん。ぼくがお百姓さんだったら、そんな雨の降る、降らないのうわさだけで神経が磨り減ってしまうのかもしれない。でもそこのところは、なんともおおらかというか、心の広さというのか、はたまた意に介せずというのか、そうでなければ世の中やってゆけないというのがお百姓さん。
いずれにしても『雨』は天からのお恵み、神頼み。そんな天の神様との「降る、降らない」のやり取りに、自然の恵みのありがたさをいちばん身にしみて知っているのはお百姓さん。ぼくもその恩恵にあずかる仕事をさせてもらっているのだから、「降る、降らない」のうわさにちょっとでいいから仲間入りさせてっ。 |
|
 |
408 野ばら
05/07/06 |
|
日本のほとんど誰もが知っている曲に『野ばら』があります。そしておそらくは『野ばら』という曲をふたつ知っているのではないでしょうか。シューベルト作曲の4拍子のリズミカルなのと、もうひとつはメロディーはよく知られていますがウェルナーという人の6拍子のメロディアスのもの。
このふたつの『野ばら』を歌い出してみると気づくのは、なんと歌詞がいっしょということです。これは不思議。しかし実のところふたつの『野ばら』、本来は若干歌詞がちがうのだそうです。ふたつの『野ばら』を訳詩したのは実は同じ人物で近藤朔風という明治の人。
ほんとうはこのようにそれぞれに訳詩が付けられている。そしてそれぞれが意味がよく似ている。そしてシューベルトの野ばらがウェルナーの野ばらの詞で歌われていることもあります。
そのわけは実はいずれの『野ばら』も、有名なゲーテの同じ詞なのだそうです。どうしてそれぞれに違う歌詞が付けられたのかはわかりませんが、さらにおどろいてしまうのは、このようにゲーテの詞をもとに作曲された『野ばら』は発掘されているだけでもなんと154曲もあるのだそうです。もちろんベートーベンやシューマン、ブラームスなども『野ばら』を作曲しているのだそうです(いちどそれぞれを聴いてみたい)。
それにしてもゲーテという人物は、どうやらすごい人だったらしい。ゲーテの肩書きはというと、まず詩人であり、劇作家、小説家、科学者、哲学者、そして政治家でもあった。つまりは超マルチな、おそらく世間の人気も集めるほどだったのでしょう。
『野ばら』の2番・3番
『野ばら』には2番と3番があります。でもそこまではめったに歌われることはありません。実際に知っている人も少ないわけです。その秘密はその詞の内容によるのかも。ウェルナー版の2・3番では・・
2.手折りて行かん 野中のばら
手折らば手折れ 思い出ぐさに
君を刺さん
紅におう 野中のばら |
3.童は折りぬ 野中のばら
手折りてあわれ 清らの色香
永久にあせぬ
紅におう 野中のばら |
野ばらを乙女にたとえるならば、乙女は童にあえなく奪われてしまう。野ばらはそのトゲで刺すにもかかわらず、童はあっけなく野ばらを手折ってしまうというわけです。
この詞はゲーテがストラスブール大学の学生だったころ、近隣の村の牧師の娘との恋をうたったものだといわれています。ゲーテは彼女との結婚を拒み、以後57歳まで多くの恋を遍歴した後、やっとのことで結婚。その後、妻に先立たれても72歳で17歳の乙女に求婚したといわれています。
ゲーテは1749年に生まれ1832年、82歳で逝きましたが、同世代ばかりでなく、後世の多くの音楽家にも影響を与えました。彼は自分の生涯で、束縛を嫌い、世の中の規範を嫌い、愛に生き、いつも青年であり続けた。
青年によって手折られた野ばらはあわれであったのかもしれません。その野ばらをゲーテは思い出にしてしまうわけですが、そうしてしまったことによって野ばらの赤く清らかな色香は、彼の心の中に永遠に色あせない存在となったのかもしれません。ゲーテは生涯、ばらを愛し続けました。
早速というか、今さらながら、ぼくは本屋へ行って『ゲーテ格言集』を買ってきたのでした。 |  |
|
 |
409 タクシードライバー
05/07/14 |
|
米国のかっこいい男優とくれば、ロバート・デ・ニーロ。ゴッドファーザーⅡでも出たけれど、この映画では、決定的にかっこいい。1976年、米国映画。
ベトナム戦争からの帰還兵トラビスは不眠症。夜勤のタクシードライバーをして稼ぎ出そうと、厳しい勤務にもかかわらず危険な場所も平気で車を流すのだった。彼にとってニューヨークの夜の客は、どいつもこいつも腐った奴らばかり。売春婦、ヤクザ、麻薬の売人・・。そんな世間に嫌悪感をおぼえ、夜にそぼ降る雨がそんなクズどもを洗い流してくれればいいと思っている。
大統領候補の選挙事務所に勤める女性に気を引かれ、デートをするのだけれど、無粋にもポルノ映画に誘ってしまい、嫌われて振られてしまう。タクシーの職場の同僚たちといえば、ただ毎日の繰り返しを惰性ですごしているだけ。夢も希望も持ち合わせることなく、明日も将来も何も変わりなくおとずれるであろう、あたかも運命付けられたかのような人生。そんなこんなで身辺の人間に幻滅するなか、トラビスはますます孤立してゆく。
運転するタクシーで見つけた可愛い少女(ジョディー・フォスター)。組織に売春でもさせられているのだろうそのかわいそうな(?)少女。車窓から時々みかけるうち、少女を救ってやらなくてはと思うようになる。
いつの間にかトラビスの心の中には『何かをして自分の人生を変えたい』=『少女を救う』=『クズを殺す』=『人を殺す』。というような図式が出来上がってしまう。マグナムだ、38口径だ、コルト、ワルサーと物騒にも拳銃を買い込み、『クズ狩り』のためのトレーニングまで始める始末。
手始めに、振られた腹いせか大統領候補の暗殺を敢行。あえなくSPに見つかり退散。そしていよいよかれの正義の矛先は、夜の街のあの少女をダシに甘い汁を吸っている奴らに向けられるのだった。ひとりふたりと射殺するうち、トラビスも撃たれ重症を負う。とうとう最後のひとりを少女の目の前で射殺。自分の銃で自殺を図るのだけれど玉切れ。気を失うトラビス。彼の表情には『何かをやった』という満足感さえ映っているのだった。
しばらくの時が過ぎ、英雄として報道された彼は仲間内でも「よくやった」と好評。偶然に客としてタクシーに乗車してきた、かつて映画館で振られた彼女にも、もうトラビスの心は惹かれることはない。夜のニューヨークにタクシーを流してゆく彼。しかしカメラは彼の猟奇的というか、常軌を逸した明らかに『おかしい男』の表情を見逃さないのだった。おどろおどろしいタクシー『イエローキャブ』は夜のニューヨークに消えてゆく。
| 正義なのか狂気なのか、殺人なのか、はたまた戦争なのか、生真面目と紙一重の異常としかいえない人間とそれを生み出す米国社会。世界でいちばん自由なのに、貧困、人種差別、偏見が渦巻く国。またそれを何とかできるどころか、そんな状況を踏み台に成り立っている資本主義という唯神論、経済至上主義。人種のるつぼ。世界中の縮図、米国、ニューヨーク。トラビスの狂気は米国の狂気でもあるのだろう。 |

|
|
 |
410 我が友
05/07/21 |
|
先回は知り合いの訃報に駆けつけてきた我が友が、もう数年ぶりくらいになるのだろうか、はるばる宮崎県からやってきた。なんとこともあろうに、娘の嫁いだ先の家族と孫とを連れ立っての『愛知万博』詣でとのこと。
旅行社のパックなので二泊三日の二日目は大阪の某遊園地なのだけれど、我が友とその連合いはそれを変更して愛知に先着、音羽に一泊ということになった。群馬県で社会人となっている我が友の長男も、骨董エンジンを積んだ高価ハーレーダビッドソンにまたがり音羽に到来、久々の親子再会も果たしたのだった。
ぼくはといえば用事で夜の帰宅となってしまい、やっとのことで我が友と再会。我が友、あいかわらず中学時代と寸分変わらぬ顔つきで(生まれたときから親父顔)一安心したものの、なんと我が友、前日の暑中の畑仕事で体調を崩しているのだった。
腹も下してしまい、どうにもたまらんと早々寝床。明日は自ら選んだ『万博詣で』という苦行が待っている。さらにその翌日は、娘家族との再度の万博詣で。仕方なくぼくと我が友の息子は、思いがけず盛り上がったブリティッシュロックの話題で親交を交わすのだった(これほどにも英国ロックに心酔の輩に出会うのもめずらしい)。
明けて微熱が後引く身体を引きずり、我が友はこれが人生最後になるであろう『万博詣で』へ出かけるのであった。そしてぼくはそのお供役。万博反対派のこのぼくが、まさかその本丸へ行こうとは夢にだに思わなかった。目玉の展示館などはなから無視するものの、どこへ行っても人の行列(この日の人手はなんと21万人)。
かわいそうな我が友、彼には子供のころからの持病があるのでした。神経痛。展示館のお遍路参りはまさに苦行で、おそらく彼の足は針を刺すような痛みでうずいているにちがいない。にもかかわらず、明日の孫たちの案内を思えば、そんなこといってられない。健常のぼくとてももうほとほとというのに、我が友の気迫に押され、苦行の旅を続けるのだった。いったいこの日のこの苦痛に加え、我が友、明日を無事に過ごせるのだろうか。まして、4歳の孫まで同行。
我が友、よくもこれだけの苦行の旅を耐えたもの。ゲートを出、やっとたどり着いた駐車場の車に乗り、力尽きてしまったのだった。今夜娘の家族と旅館で合流しなくてはならず、彼とその連合いを駅まで送り、それではいお別れということに相成る。なんとあっけない久々の親交なのだろうか。
考えてみると彼、我が友との再会はいつもなぜかあっけない。彼が酒飲みでぼくが下戸だからだろうか。下痢と万博のふたつ巴のおかげだろうか。はたまたお互いわかった者同士で、言葉なぞ必要ないからだろうか。
今度の正月にはぼくらが宮崎へあそびに行くからという固い決心を、すでに実家にたどり着いた彼に電話越しに話すぼくだった。そして彼、結局連日の苦行はたまらんと、孫にもそれはたまらんと、最終日の『万博詣で』は親戚一同協議のうえ、中止にしたとのことだった。うーん、仕方なかろう。 |

我が友夫婦と息子(右3人) |
|
 |