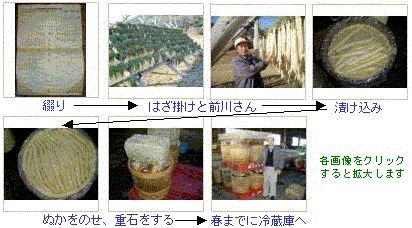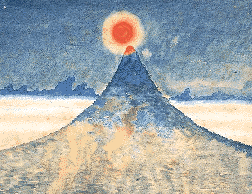431 年末年始風景
05/12/27 |
 |
最近では年末歳末、正月だからといってどの店も総仕舞ということがなくたった。大型店、コンビニとこのときとばかりに集客する。けれどかつての日本では歳末大晦日のころともなると、正月三箇日をのんびりと過ごすための仕入れとばかりに、街は人々でごった返していたもの。目抜き通りで定期的に行なわれる露天の市、公設市場や商店街などは普段でもにぎやかだったけれど、このころばかりは尋常な混雑振りではなかった。光り輝くモールなんぞで飾られた恒例の歳末大売出しの看板が挙がれば、身も心も『師走』に突入。
子どもたちはといえば、冬休み、クリスマス、プレゼント、大晦日、正月、初詣、お年玉と、一年でこれほどしあわせに満ちたときもなかったもの。寒くても、外では焚き火で焼き芋。羽根つき、凧揚げ、独楽回し。家の中ではあったかやぐらコタツに火鉢。焼きするめに焼餅、カルタに双六、ババ抜き、七並べ。だからぼくらは冬休みの前の終業式のころには、今に思えばなんともはかないけれど、ほんの2週間ほどの年末年始を夢に見るのだった。
どうせ禄なものも買ってもらえないけれど、母親の買い物籠のツルにつかまってはついていった近くのマート。おせちの材料を買い求めるにも、セルフサービス方式の今とちがって相対の売り声が歳末の気分を盛り上げる。魚屋のオヤジの威勢のよい『ラッシャイ』の呼び込み。八百屋はモンゴルのホーミーを彷彿とするようなだみ声。数の子だ、するめだ、蒲鉾、新巻。みかんだ、芋きり、りんごにレンコン。買物の荷物を『持つ』という約束で買ってもらう『おまけつきグリコ』。街は活気に満ちあふれ、いっせいに繰り出してくる主婦やその付き添いの旦那や子どもで、押し寄せる『人の波』とはこのこと。おそらくは今よりは確実に人口も少なかったわがふるさとだったけれど、とにもかくにもすごい人混み。
『ジングルベル』や『お正月』が割れんばかりの音量でラッパ型のラウドスピーカーから流れる。売り声と「高い、負けろ」の掛け合い。箱から取り出す三角くじ。八角の抽選機からポロリと出てくる色の玉。時折聞こえてくる特設の抽選会場からのチリンチリンのリンの音。子どもの泣き声、迷子のアナウンス。すべての人たちが、いうならば明日や来年のことよりも、まずは今を生きることに精一杯。足早に歩く母親に、ついてゆくのが精一杯の子どもたち。
時代は変わって現代となり、不景気といえども街は絢爛な『もの』であふれかえっている。なのになぜかそこには喧騒がない。買物がセルフサービスだからなのか、お上品になったからなのか、財布と相談しなくとも、カードで『もの』が買えるからか。ポータブルプレーヤーのヘッドホンからは、どうせすぐに消え去る安物の音楽。人たちは『波』をつくることもなく、無言でと師走の夢をかなえてゆく。
むかしの人たちからすれば、高嶺の花とも思える現代の夢。整然と時が流れてゆくだけのような師走だけれど、せめてささやかな夢に胸膨らます気持ちを忘れずにいたいと思う。 |
 |
432 食と農
06/01/10 |
|
『地産地消』という言葉は、農水省の1981年からの4年計画『地域内食生活向上対策事業』というのから発生した言葉とのこと。この事業は、戦後の高度経済成長に立ち遅れた、農村社会の生活水準向上を図る目的で行なわれてきた『生活改善普及事業』の一環で打ち出されたもので全国8府県で実施された。伝統的な日本の食文化での塩分の取り過ぎやカルシウムなどの不足しがちな食生活を改善する。また地域内生産の食料の地域内消費を実施する、いわば地域自給を目標とした。
ここでちょっと問題としたい点は、これはニュアンスなのだけれど、それまで貧弱であった山村地域の『食』の改善が目的であって、たとえば韓国で伝統的にいわれてきた『身土不二』が意味するところとはちょっとちがう。
この『地域内食生活向上対策事業』というのが好成績を得たかどうかについては推して知るべしだけれど、とにかく『地産地消』なる言葉は一時その目的を失い、影を潜めていたといって差し支えないと思う。『身土不二』が韓国から、『スローフード』という言葉がイタリアから、『フードマイルズ』が英国から日本に紹介されるようになり、さらに日本の食料自給率の低迷の中、食と農の行く末を案じてか、これではいけないとそれらに対抗する言葉として持ち出されたのが『地産地消』ということにもなりそう。
1971年発足した日本有機農業研究会。こちらでは1978年、会の創始者一楽照雄氏が『生産者と消費者の提携』という10項目の中で『産消提携』という言葉を使っている。これは言うまでもなく、生産者と消費社が提携する中で食農文化を築いてゆこうという意味。そのためには生産者と消費者は、互いに顔の見える関係でなければいけない。いうならば、本来の意味をあらわす言葉は、日本では『産消提携』の方といえる。
まわりくどい話になってしまったけれど、おそらくどの国、どの地域にもこれらの言葉を意味するものがあるにちがいない。ことわざにも『郷に入ったら郷に従え』なんていうのもある。
人は何のために食べるのだろう。テレビを見れば『食べ歩き』だ『グルメ』などと興味をそそる。あるいは食べるとは、食欲を満たすことなりなどと・・。今さらいうまでもないけれど、『食』とは『医食同源』とも言うように、私たちが健康を保つための行為に他ならない。
では『農』とはなんだろう。いうまでもなく『農』とは、単なる生産活動とはちがう。その基本は『自給』ということがいえる。自分で食べる分を自分で給するということになるのだけれど、たとえば『地域自給』『流域自給』というように、やっぱりこれも有機農研の言葉を借りるなら『産消提携』ということになる。
ぼくが言いたかったのは、農と食とは切っても切れないきずなで結ばれているということ。それは言葉を換えれば、農=生産、食=消費ということであり、農は土であり、食は身である。さらに土は環境であり、身はわたしたちの健康である。つまり私たちは環境と『=』で結ばれる。あたりまえだけれど、すごいと思う。
|
 |
433 ローリングストーンズ
06/01/26 |
|
1963年チャック・ベリー(50年代後半売れに売れた米国黒人R&B奏者)の曲でデビュー以来、なんと40年以上活動を続けているすごいロックバンド、ローリングストーンズ。おそらくは歴史に残るならビートルズなのかもしれないけれど、やっぱりその実力というかロックの本筋といえば、なんといってもこのローリングストーンズ(以後ストーンズ)といえましょう。
ストーンズの起源はといえば、1960年ロンドンでふたりの黒人音楽好きの青年、ミックジャガーとキースリチャードが意気投合したのがきっかけだったといわれています。さらにやはりブルース狂のブライアンジョーンズが加わった段階で、ストーンズは誕生した。1962年。このローリングストーンズという名のゆかりはもともとブルースの曲名によるもの。
それはスキッフルブームの中で生まれた
ロンドンといえば文化の中心。音楽においてもそうで、当時黒人音楽であるブルース、ジャズ、ソウルといった音楽を、英国流の感性で演奏しようという『スキッフル』というブームの中、若者たちはいろんな解釈で黒人音楽に入門していったのだった。これは一般的には知られていませんが、その中心的な役割を果たした人物にアレスシス・コーナー(1929ー1984)という人物がいます。自らのバンド名は Alexis Korner's Blues Incorporated といい、数多くのブリティッシュロックミュージシャンを輩出しました。いわば英国ロックの大御所、登竜門。おもだったところでは、ヤードバーズ(後のレッドツェッペリン)、フリー、ロッド・スチュアート(フェイセズ)などなど。
われらがストーンズもその真っ只中に飛び込んでゆき、自分たちよりもずっと年上のアーティストたちにもまれながら確固たる方向性を得てゆく。『スキッフル』がブルースやジャズ、ソウル、R&B、ロックンロールなどと多義にわたったのに対して、ストーンズは若さゆえにロックのリズムを優先する曲を演奏することとなっていきました。
60年代、当時ストーンズがいくらがんばっても、いつも比較対照され、人気を先取りされていたバンドとしてビートルズがありました。ビートルズはストーンズとはちがっていて『ブルース』をその音楽的起源としていませんでした。ビートルズはいうならば『白人音楽』の中から生まれたといっても過言ではありません。かれらはオリジナリティー豊かな曲の数々を生み出しましたが、そこには黒人音楽と英国の音楽を融合させたスキッフルを発展させたかたちでの音楽性があります。
それに対してストーンズの場合は、60年代後半、サイケデリックブームもあり、またビートルズとの競り合いもありで、オリジナリティーをもっと膨らませた曲を含んだアルバムを出していたこともあります。それはブライアンジョーンズの個性のおかげではありましたが、なんと69年のブライアンの脱退、死でふたたびというか最終的に黒人音楽(ブルースとソウル)を基本とするバンドとして定着してゆくのでした。
そんな中、ロックはやはりブルースを基盤に、重く、泥臭く、ヘビーな方向に進んでゆく。クリーム、レッドツェッペリンなどのハードロックの時代へと突入していきます。ビートルズのサイケデリックというか、ポップ路線とは歩調が合わなくなっていってしまう。だから1970年のビートルズの解散というのも、まんざらうなづけないともいえないのです。
黒人音楽は現代の世界のポピュラー音楽、とくにロック音楽に大きな影響を与えました。ロックは黒人音楽を白人の若者の気質で継承する中で発展してきた音楽です。その根底にあるのは黒人の歩調からうまれたリズム『ブギー 』の2ビートであり、そしてこれは黒人音楽の『命』の部分、つまり差別の中で、なんとか幸せになりたい。音楽がそのための叫びであり、希望だった。
今では米国に渡り、国民的な歌手となったロッド・スチュアートはこんなことをいっています。「アイルランドの貧しさから抜け出す方法は、ぼくらにとってふたつあった。サッカーか音楽。そしてぼくは音楽をえらんだんです」。
数多くのすばらしいロック音楽の歴史の中、やはり多くのミュージシャンやバンドが生まれては消えていきました。ではどうして『ローリングストーンズ』は今も残っているのでしょう。それは彼らがはじめにも終りにも黒人音楽そのものを基盤とする音楽(普遍的に変わらない)を続けてきたからなのだと思う。
それにしても40年も続いたとはすごいですね。 |  |
|
 |
434 GMナタネの野生化
06/01/25 |
|
日本の原風景といえば一面を覆いつくすばかりのれんげや菜の花。もっとも最近では菜の花(ナタネ)などは油を絞るためでなく、観光も兼ねた景観作物として休耕田などで栽培されたりしています。
ナタネがオールシーズンで
でも、栽培されなくても、また、真夏や秋、冬でも菜の花が咲いているところがあったりするのです。その場所はナタネの輸入港の周辺、そしてそれを原料に食用油を作っている会社にむかう道路脇です。そしてそこで花を咲かせているナタネが、実は遺伝子組み換えだったりするのです。
この事実は一昨年夏、千葉県鹿島港周辺で起こっているとして農水省によって公表されました。名古屋では遺伝子組み換え食品を考える中部の会のメンバーで、早速四日市港と名古屋港の周辺を調査しました。といてもとりあえず下見のつもりで出かけた調査でした。
ところがおどろいたことにまったく季節外れのお盆の最中にもかかわらず、たくさんのセイヨウナタネが自生していることがわかったのです。しかも花まで咲かせて。そしてさらにおどろいたことに15箇所でみつかったセイヨウナタネのうち、6割が除草剤耐性GMナタネだったのです。その後、秋、冬、そしてもちろん春にも調査を重ねましたが、どの季節にも量の差こそあれ、セイヨウナタネの自生が確認されました。
オールシーズンの意味すること
季節に関係なく、いつでもセイヨウナタネが咲いているということはどういうことでしょう。要するに一年中セイヨウナタネがこぼれ落ちているということです。製油会社へのナタネの輸送トラックが走っている限り、それが止むことはありません。トラックがタネをまいて走っているということになります。
GMナタネが自生していてもいいのか
では、これらのGMナタネが何の管理もされないままで、道路脇や田んぼの畦で自生していてもいいのでしょうか。その答は法律的には『Yes』です。今のところ見つかっているGMナタネはいずれも、食品として認可がされていて、作物として栽培してもよいことになっているのです。では問題がないから、野放しにしておいていいのかというとそうでもない。
GM作物は日本ではまだ一般には栽培されていない
たとえ食品として、また栽培も許されていても、日本ではまだ一般の農家ではGM作物の栽培はされてはいません(栽培が強行され、中止させられたことはありますが)。一応は食品として、また環境に対しての安全性が確認されているのにもかかわらず・・です。では、どうしてでしょう。
その答は簡単です。それは、消費者が望んでいないからに他ありません。消費者に受け入れられないものを栽培しても意味がないばかりか、信用を失いかねないからです。また、周囲の同じ作物を作っている農家に迷惑がかかるからです。GM品種が交配によって、非GMを汚染するかもしれない。またはその疑惑で、周りの農家からも信用を失ってしまうからです。
それなのにGMナタネが道端で咲いている
日本の生産者も消費者も望まないGM作物がいつの間にか自生してしまっている。これはいったい、どう判断したらいいのでしょう。いうまでもなく、ナタネは雑草にもなり得る作物です。現にカナダでは除草剤で枯れないナタネが雑草化しているのです。そして日本でも。
認証済みGM作物は安全なのか
今の段階では環境安全性が確認されていることになっているGMナタネですが、実際のところは『わからない』。実は目に見えないところで危険があるかもしれない。アレルギーの原因になるかもしれない。また自然界では在来種を駆逐してしまうかもしれない。実は悪影響があらわれるのかもしれない。いったん環境に放出されてしまってからでは、もしかすると取り返しのつかない結果になってしまうのかもしれない。
その答がわからないからこそ、GM作物は慎重に扱わなければならないのです。
詳しくは
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/sa-to/gm-natane.htm
をごらんください。 |

四日市港にて04/07/21 |
|
 |
435 前川さんの一丁漬
06/02/01 |
|
いつも道長の細かい注文に応じてくださっている前川漬物さん。その歴史についてはすでに道長のホームページでお知らせしていますが、当代の吉之助(きちのすけ)さんは漬物屋としては2代目。そして実は先代の彼のお父様(弥七さん)が戦後まもなく、残念なことにたった49歳という若さで逝ってしまわれた。にもかかわらず弥七さんは、なんと一代で大根の栽培、渥美の一丁漬をものにしたのです。
もともと前川さんは代々地元で味噌屋さんをしてみえました。しかし太平洋戦争勃発となり、それまで大豆の需用の半分以上を輸入に頼っていた日本では、それがままならなくなり、1940年、とうとう大豆も統制ということになってしまった。原料がないのでは仕方ないため、前川家は味噌屋さんをあきらめることとなる。農家もしていて畑もあり、大根を作って漬ける仕事へと転職。当時人口甘味料や着色料が出回ったころで、高い塩度でもそのおかげでうまい(?)沢庵漬ができました。
今回、そんな吉之助さんのお父様の努力の一端を覗えるともいえる貴重な『資料』を見せていただくことができたのでした。その資料とは、最近になって前川家で見つかったという一丁漬について記された綴り2冊。なんとその綴りは先代が漬物のノウハウを構築すべく、漬け込みからその後の経過をつぶさに記したものだったのです。それぞれの綴りには『一丁漬漬込及経過表』とある。そしてその綴りを開けてびっくり。
極細の、今は懐かしいガラスペン(注)で書いたと見られるいかにも達筆な繊細な文字。一枚づつが表になっていてその都度のデータがぎっしり。考えてみれば、その日付にある昭和25年ごろ(なんとぼくは26年生まれ)にはコピーなぞない時代。一見同じ書式の表をよくみると、一本づつの細線がペンで書かれていて、その起点に小さな穴があいている。むかしたくさんの半紙に同じ書式の表を書く場合、重ねた何枚もの紙に針を打って目印とし、直線を描いて作ったもの。いかにも几帳面という性格が見えてきそう。
なぜにと思い、吉之助さんに伺って納得。彼の父、弥七さんは役場の戸籍係をしてみえたとのこと。もしかするとこれらの表の書式、役場での仕事の合間に作ったのかも知れない。
吉之助さんがまだ十代のころ、父弥七に促され、大根の収穫、寒干しのためのはざ掛け、一丁漬の漬け込みなど手伝わされた。そして吉之助さんも漬物の仕事を継ぐこととなった。
当時は渥美の多くの農家が一丁漬のための大根作りをしていて、冬には海岸に近い場所に延々と続く大根のはざ掛けが見られ、壮観であったとのこと。しかし昭和40年ごろ、若くして弥七さんが亡くなったあと4、5年で一丁漬を漬けることはなくなった。時代はぬか漬を好まなくなってゆき、麦のフスマで漬けたり、液漬け(塩蔵大根を塩出しし、再び調味液で漬けなおす)にしたりするようになった。主流は中国からの輸入塩蔵大根へと移ってゆく。
| じつは今回前川さんを訪れたのは父上の綴りを見せていただく目的の他に、もっと大きな目当てがあったのです。なんと彼にとっては40年ぶりの、一丁漬の試作をお願いしたのでした。今年で60歳の大台にのってしまったとはいえ、久々の一丁漬の漬け込みに吉之助さんは少々興奮気味。当初試験的にお願いしたつもりが、白首大根を作って、見事な寒干しのはざ掛けまでも本式に。本格的に4斗の木樽でのまさに一丁漬(4斗樽ひとつを1丁と呼んだ事からこの名が付いたといわれています)を実現してしまったのでした。しかもなんとその木樽20丁。 | |
これまでして奮発していただいたからには、「前川さん、がんばって売らせていただきます」と固い約束をし、1/29の訪問を終えたのでした。 |
 |
436 宮崎の我が友
06/02/15 |
|
昨年夏久々九州宮崎から遊びに来た我が友のところへ、今度はこちらから訪問。年月を指折り数えてみれば、先回ぼくが我が友を訪れたのはちょうど今から30年むかし。ぼくも我が友も若干24歳のとき。そのとき以来、我が友は三度ほどぼくを訪れてくれたのに、ぼくは一度も。
漬物屋とは生ものをあつかっているという都合と、貧乏閑無しの典型のような仕事で、なかなか連合いとそろって旅行というわけにいかない。それとぼくの連合いはといえば、これまた貧乏性とでもいうのか旅行などというととたんに出不精となる。
今回九州宮崎くんだり出掛けたによっては、我が友との約束があったからなのだけれど、それでもやっぱり久々の旅行ということで、さらに我が友との再開ということで胸わくわくといったところ。どうせなら『行ってきた』の実感がほしいとばかり、自家用車を駈っての往復2200キロの行程。高速道路で結ばれているとはいえ、やはりちょっとたいへんなので、下の息子を運転の交代要員に起用(折りしも西日本に大寒波襲来で散々な目にもあってしまったのだけれど)。とにかく雪にもめげず無事宮崎に到着できたのだった。
中学のときぼくと我が友は出会ったのだけれど、彼、なんとも陰気くさいというか目立たないタイプだった(いじめられっこだったそうだ)。ぼくがそんな我が友のどこに興味をそそられたのか、という疑問についてはいささか決定的な回答を得るのがむつかしいのだけれど、やっぱり彼がちょっと『変な奴』だからかもしれない。
この『変な奴』という言葉には、いろんな深いニュアンスが含まれている。とにかく我が友、必要以上に気を使い、必要以上に我慢強く、頑張り屋で、負けず嫌い、心配性。長所と短所がそれぞれけっこう極端なのだけれど、にもかかわらず、底力でもってして苦境を跳ね除けてしまうところがすごい奴。
そんな我が友の性格とはちょっとちがって、ぼくの場合は(意識的に)気を遣わない。我慢するのが苦手、せっかち、長期的に見て頑張り屋(継続は力なり)。あとは負けず嫌いの心配性。
ひょっとすると我が友に出会った中学のころ、いつも独り居た彼の、いつも何かを耐えているかのような、考えているような、一点を見つめて答を出そうとしているのか、時間の経過を待つような、少年らしくない静かさというか奥深さのようなところに心を惹(ひ)かれたのではないかしら。たぶんぼくの周りでいちばん変わっていた。
けれど、実はそんなこと上辺の彼だったのかもしれない。出稼ぎの親に連れられて遠く故郷から離れ、もしかすると彼は孤独で、ともだちがいなくて途方もなくさびしかったのかもしれない。自分の生まれたところを離れる必要もなく、父親には定職もあり、貧しいながらも恵まれたぼくなぞ別世界だったのかもしれない。
これはほんとに皮肉かもしれない。気を遣う我が友と、気を遣わないぼくがなぜか付き合っている。ちょっと変だけれど、我が友も変な奴かもしれないけれど、やっぱりぼくも変な奴なのです。 |
我が友と奥方 |
|
 |
437 串原村のゴーバルさん
06/02/15 |
|
岐阜県恵那市串原村というところで、食肉ハム・ソーセージの加工販売をしている『ゴーバル』という工房がある。現在ゴーバルさんは石原さんと桝本さん二組の夫婦が中心に運営されているのだけれど、その石原さんのご両親が1974年、名古屋から串原に移り住んで、民宿『ゴンチャボハウス』を開いたのが起源とのこと。そこへ農業志願の彼らの息子弦さんと桝本さんを含む3家族が加わり『アジア生活農場ゴーバル』を発足したのだった。その年1980年。『ゴーバル』とはインドなどの中央アジアで『牛の糞』を意味する言葉だそう。その当時は山間串原ではさぞかし稀有な存在であったのかもしれない。
とにかくゴーバルさんのほかとちょっとちがうところは、安全性の追求もさることながら、なんといってもあくなき『味』への追求。基本的にハムとは肉の『漬物』という桝本さんの言。となれば十分に納得もいくというもので、上等な肉を単純な方法でいかにおいしくいただくか。しかも大切ないのちをいただくのに、そのときだけでなく、時間をおいてさえおいしく・・。薫煙などして水分を抜き、低温殺菌する、または塩蔵する。基本の味となるのは塩であり、肉の臭みを和らげたり、風味を引き立てたりするためのスパイス。
工房の中で興味津々となったのはまず肉を漬け込むための塩水。とはいえすでにその塩水はスパイスが加えられて、黒く得体の知れないというかなんとも魅力的な調味液となっている。この中に漬け込まれた肉は一体どんな味になるのだろうと、想像するだけでも楽しくなってしまう。それと薫煙装置。薫煙とはまたまた奥が深いようで、素人のぼくが講釈できる代物ではないけれど、酵素や乳酸菌などの微生物の働きを妨げない低温でするところがミソ。

熟成中の生ハム |
これすべてスパイスのストック
 |
ゴーバルの味は、もしかすると桝本さんのあくなき探究心の賜物なのかもしれない。塩とスパイスへのこだわりがその証拠で、塩はモンゴル産の岩塩と天日塩を使い分けている。スパイスについてはさらにびっくり。ゴーバルの0℃に保たれた冷蔵庫には、ざっと見渡しただけでも十数種類もの本場から取り寄せたスパイスが保管されている。それらを微妙に組み合わせて、各種のハム・ソーセージに風味をつける。
ゴーバルさんでは特製のカレーの素も販売していて、その基本の配合を完成するため、桝本さんの家では延々カレーの日々を過ごしたことがあるとのこと。道長で使っているスパイスといえば、せいぜい唐辛子としょうが、にんにくといったところ。桝本さんからスパイスについての『勘所』の一端も教えていただいた。 |
『保存食』としての肉は世界中でいろいろな形がある。寒冷な欧州では、ハム・ソーセージとして。乾燥した中央アジアでは乾物にして。そして暑かったり、水が悪かったりするインドなどの東南アジアでは、その日のうちにそのすべてをみんなで平らげてしまう。日本の場合はどうなのだろうと考えてみると、はてさて肉とはどんな位置付けとなるのだろう。もともと食べるつもりはないのだけれど、たまたまそんな機会があればありがたくいただくというのがそれかもしれない。もちろんそれは限りなく贅沢な、自然からのありがたい恵みなのではないかしら。
ハム・ソーセージたっぷりのお昼ごはんまでご馳走になり、感謝感激。みなさまどうもありがとう。 |
若々しいゴーバルさんのメンバーと |
|
 |
438 写真
06/02/28 |
|
最近はデジタルカメラが普及したおかげで、写真というものがかつての何かを記念するような特別な目的から、とりあえず書き留めておくというような、消去可能な日常的なものになった。
ぼくにとっても、デジカメで撮った写真が、これは一生残したい記録なのか、はたまた後々の何かの見直しのために必要な記録なのか判断しにくかったりするもの。そもそも写真とはいったいどういうものなのだろう。
写真がなかったころには、ある場面を記録しておくために絵を描いた。その多くは何かのメッセージのような目的であったりする。もっともそういった類の絵だからこそ、人に目立ち、消えにくい部分に描かれたのだろう。具体的な内容としては、歴史的出来事、支配者などの様子など。けれどそれらは文字などとともに、あくまでも記録として意義はあるけれど、個人の深い『思い入れ』などとはちがっている。
それでは、それくらいむかしにそういう類の絵は描かれたのだろうか。それはたぶん、というよりはきっと描かれた。けれど残念なことに、それらは長い年月のあいだに風化し、消え、もう残っていない。もしかするとそれらの絵はすごく個人的なものであったのかもしれない。それを描いた本人にとっては重要なものでも、他人にはあまり関係なかったりするという理由で、その本人が居なくなればその絵の存在意義もなくなってしまうから。
ぼくたちがかなり重要だと思って残している写真がある。アルバムに貼り、後々それを見返してはむかしを懐かしむ。はっきり言って大切な思い出の写真。
ぼくの家にも、それこそセピア色にあせた写真が貼られている昔々のアルバムがある。これがぼくが生まれる少し前に死んだ祖母。もっと前に死んだ祖父。そんな写真の中に、まったく見知らぬ写真が少なからずあるのに気付いたりする。この人はいったいだれなのだろうと思って、年取った母に聞いてみると「たぶん誰々だろう」と遠い記憶をたどって彼女は答える。でも、たしかに何かの思い入れでそのときは貼られた写真であろうけれど、それが頼みの綱の母でさえさっぱりわからない人物であったりする。こうなってくると、せっかく大きな意味もあったであろうはずの記念写真も何の意味もないただの代物となってしまったりする。そう考えてみると、写真とはなんとも「はかない」ものなのかもしれない。
 |
印画紙に転写されて記録された写真は、一見すると物質的なもののような錯覚があり(もちろん普遍的な物質などありえないけれど)写真とはずっと残るもののように考えられる。けれど、それに何かの『思い入れ』がなければそれはただの画像に過ぎず、必要のないものとなる。ちょうどアルバムに貼られた写真が、時とともに色あせ、セピア色にかわってゆくように、人の記憶からもあせてゆくのかもしれない。
デジカメのおかげで気軽に写真が残せる世の中ではあるけれど、もういちど、写真とは何だろうと考え直すことも肝要なのかもしれない。はかないからこそ、大切なのだから。 |
|
 |
439 未来への伝言
06/03/16 |
|
1960年ごろ、ポリオ(小児マヒ)が世界的に流行った。ぼくと同じ学級にもそのおかげでからだが不自由な子が居たもの。彼は差別的なあだ名を付けられても、ある意味で特別な扱いを受けながらも、あかるくはきはきと学校に通っていた。それが日常だったためか、ぼくたちも大した違和感を感じることもなく彼との学校生活を送った記憶がある。この映画の製作は1990年、日ソ合作。
この映画ではポリオを克服すべく、当時ソ連で開発され絶大な効果を発揮していた『生ワクチン』を日本でも、というのが、幼子を持つ母親としての気急の願いだった。そんな状況の中、薬事法を盾にした薬剤業界、国、政治の軋轢を克服してのソ連との輸入交渉。日本も日本ならソ連もソ連。渋るもの同士をつなぎ合わせるための、日本の主婦、ソ連の医学者たちの苦闘する様が描かれている。運動の主体となる圭子という女性に栗原小巻(吉永小百合と並んで、ぼくらの青春のアイドルだった)、ソ連側からも第一級の役者が顔をそろえている。
当時の日本とソ連の関係は東西の冷戦という状況もあり、平和的な関係を築こうとする動きに対しても、国や関係業界などはすこぶる冷ややかであった。それでいて相手国の不穏な空気には、いち早く反応するという状況。
血のにじむような運動の結果、日本のポリオが鎮圧されたことは、この映画の結末からしてとても喜ばしいことであるはず。以後現在に至るまで、ポリオ罹(り)患率は99%以上減少したといわれる。にもかかわらず、この映画では、なんとなくその結果について明朗な表現をしていない。60年ごろ、こういうことがあったという歴史的事実が銘記されているにはちがいないのだけれど。
それには、この映画が1990年に製作されたということで理解ができるのかもしれない。どういうことかというと、たとえばこのような人々の努力で獲得されたポリオの克服という『安全』が、その後の生命や食の安全のために確実に受け継がれたとは言い切れないからだと思う。薬害エイズ事件、サリドマイド、水俣、スモン、ヒ素ミルク。食の安全、雪印、狂牛病、遺伝子組み換え。どれをとっても政治となにかが関係したりしていて「またか」といいたくなるようなことばかり。

| すでに長男をポリオで亡くしている圭子(栗原)は、我が子に生ワクチンを与えるためソ連へ渡った |
|
あることの安全が担保されないことがあり、それをとりもどすための運動をそれぞれの場所地域でそれぞれの当事者たちが行なう。しかしながら、そこでの運動の過程、結果がほかの運動に生かされないことが多い。それはそれぞれの例があまりに地域的であったり、特殊だったり、またその突破口が異例だったりで、他への応用が利きにくいことがおおい。そしてさらに、当事者はその問題に心血そそぐことで精一杯で、その力を他に注ぐ余力がないこともあるのだろう。
少なくともこの映画で表されていることは、愛する子どもたちを病魔から守るため、全身全霊が注がれた。そして結果として子どもたちは守られた。この映画はそれが実現される過程を記録したもので、現実にあった出来事なのだということを明記している。そしてその事実を『未来への伝言』としようということに他ならない。 |
|
 |
440 オノマトペと賢治
06/03/23 |
|
ラジオを聴いていたら、はじめて耳にする言葉が流れたのだった。その言葉とは『オノマトペ』。このぼく、この世に生を受けて50年以上になるけれど、こんな単語があることすらついぞ知らなかった。
おかげでそのラジオ番組の内容なぞどうでもよくなってしまい、早速調べてみると『擬態語』『擬音語』などという意味のあるフランス語なのだそう。綴りは onomatopee。たとえば雨が『しとしと』と降る。太陽が『さんさん』と輝く。思わず胸が『グッと』締めつけられる。ネコが『ニャーニャー』鳴く。『クイッと』一杯やる。などなど・・・。オノマトペとは修辞技法(文章の表現をするための技法)ということができる。
ぼくが実感しているわけではないのだけれど、欧米では修辞技法は数多くあるものの、日本語のように連用修飾語というか副詞として、名詞以外のおもに動詞に付属してその表現力をアップさせるような目的で使われるオノマトペはめずらしいとのこと。たとえばコミックなどでは『 Bang 』とか『 Woop 』、『 Zzzz 』など擬音語には事欠かないけれど、あくまでもその状況をその語自体で表現する場合が多い。
日本語で『ぶつぶつ文句を言う』というけれど、英語の場合には『 Murmur 』のように擬音というか擬態語としての意味をもっていて、それ自体が単独で意味を持つ動詞だったりする。それに対して日本語の修辞技法では、動詞をさらに修飾して、たとえば『飄々(ひょうひょう)と歩く』、『凛(りん)とする』、『ガツガツ食べる』『カンカンに怒る』、目を『爛々』と輝かせる。『シュッと』したいい女などと表現して文章を引き立てる。
ここからが本題。独特のオノマトペでちょっと変わった世界を表現するのが宮沢賢治。かれは自ら創作した擬音や擬態をたくみに使って物語を作っている。たとえば『かしわばやしの夜』という物語の中では、おつきさんおつきさんまんまるまるるるん/おほしさんおほしさんぴかりぴりるるん/かしわはかんかのかんからからららん/ふくろはのろづきおっほほほほほほん。さらに、雨はざあざあざっざざざざざあ/風はどうどうどっどどどどどう/あられぱらぱらぱらぱらったたあ。といった具合で文章をリズミカルで音楽的な雰囲気に仕立てている。
|
この『かしわばやしの夜』はなんとも意味のわからない話だけれど、ちょうど野口雨情と中山晋平が1924年発表した『証城寺の狸囃子』で和尚さんと狸が月夜の境内で浮かれる様子に似ている。そしてなんとこの『かしわばやしの夜』もそれと同じ年の12月に発表されているのは単なる偶然でもないのではないかしら。どちらが先なのかわからないけれど、宮沢賢治もやはりこの物語を音楽として表現したかったのかもしれない。『証城寺』もおかしな世界なら、『かしわばやし』も然りで、音楽劇、ミュージカルだとすれば、なんとも楽しく、遊び心満点のものとして考えることができる。
日本語はそれ自体音楽的なリズムを刻みにくい言語といえる。その中にあって、オノマトペはそれを補足するのには持って来いの技法なのかもしれない。 |
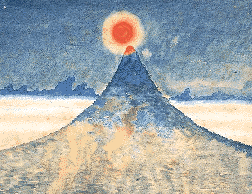
宮沢賢治『日輪と山』 |
|
 |