 > >
|
 「近代の奈落」 宮崎 学 【解放出版社】 「近代の奈落」 宮崎 学 【解放出版社】 |
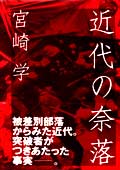 宮崎さんご自身のサイトで知り、買ってみた。かなり分厚い本なのだが、実際に読むと面白く、最近本から遠ざかっている私にしては割合に早く読了できた。 宮崎さんご自身のサイトで知り、買ってみた。かなり分厚い本なのだが、実際に読むと面白く、最近本から遠ざかっている私にしては割合に早く読了できた。少しだけ目次のタイトルやサブタイトルから引用して紹介すると・・ 「川筋のボタ山に立つ」、「柏原三青年と全国水平社」、「京都部落解放運動の光と影」、「アナ・ボル対立と平野小劔・高橋貞樹」などなど。 筑豊の川筋者の解放運動には、「すごい!」と唸りながら読み、「オール・ロマンス闘争」の裏側にあった事実にも考えさせられた。アナ・ボル対立のところは少し難しかったが、平野小劔や高橋貞樹の人間としての生には興味が湧いた。水平社創立宣言の多くの部分が平野の手によるものだという研究のあることもここで初めて知った。 自らの足で「近代の奈落」である被差別部落を歩き、話を聞きながら著されたこの本の文章群は、私にとっては、今までの知識にはない新鮮なものであった。宮崎さんの感じ方、考え方にも、どこか同質なものを見つけ、惹かれてしまう。転勤で忙しすぎて、2ヶ月前に読んだこの本のUPが今日まで延びてしまった。でも何度でも読み返したくなるような魅力のある本だというのが、私の正直な感想だ。(2003年6月) まず最初は、「突破者から見た解放の父−もう一つの松本治一郎伝」から引用する。 |

| (P48〜P51より) 「神様」と「人間」 (前略) 松本さんの写真を箱に入れて枕元に飾っとる。写真の前にローソクと線香が立てちゃったね。いつも手を合わせて拝みよんなさったですな。 (鞍手町の和田七郎老人の回想) 天皇の「御真影」と松本治一郎の写真を並んで飾っている家もよく見かけられたという。 人間が仲間全体の父になったり、神様になったりするのは、容易なことではない。彼がなろうと思わなくても、みんなの役割期待が、ならせるのであるが、その役割期待が全体の「父」や「神様」であるとき、それに応えるのは至難の業である。 それに応えきったところに、治一郎の偉大さがある。 なぜ応えることができたか。 一つは「無私」であろう。自分を捨てている。だから、期待されるとおりの役割をする。 そのための決意は並々ならぬものだったろう。一升酒を飲んでいたのが、解放運動に入ってからは「万年被告」と称して酒も煙草もやめ、生涯守っている。いつでも監獄の中にいるつもりで生活するというのである。なかなかできることではない。私のような、いいかげんな人間には想像を絶する。 もう一つは、逆説的に聞こえるが、人間を「役割として」だけではなく、「人格として」見る見かたを貫いたからではないか。 役割と人格 人間はいろんな役割を負わされて、それを果たさねばならん。だが、人間は役割を生きながらも一個の人格として生きる。 治一郎は、政治権力や社会権力と闘い、その手先とは厳しく対時したが、人格としての彼らを「敵」とはしなかった。 筑豊の鉱害闘争で会社側暴力団や官憲と対決したときのことを、解放同盟福岡県連委員長・羽音豊は語る。治一郎は、彼らヤクザ者や警官と闘いながらも、「君たちは、上の指示でやっておるのだろうが、やめなさい。君たちは敵ではない」といったという。役割としての暴力的妨害分子は敵だが、人格としての個々のヤクザや警官は敵ではない、というわけである。 また、合化労連委員長だった太田薫によると、一九五二年、宇部窒素の争議で、広島からヤクザが動員され、会社が雇った請負師が争議団と対時したとき、治一郎は、ヤクザには足賃を払い、請負師には「あんたたちは会社に雇われているのだから会社を守ることはいい。だが、太田君らは会社に打撃をあたえようとしているのではないから、争議団には手を出すな」と説得したという。 一九四八年、「カニの横ばい事件」(参議院副議長として天皇に「拝謁」するのを、「人間が人間を拝むようなまねはできん」といって拒否した事件)のとき、天皇とこんな会話を交わしている。 治一郎「天皇、きょうはご苦労さんです」 天皇「いろいろとご苦労です」 これは治一郎の平等思想、ユーモアを示すものとして語られているが、私は治一郎が面と向かって天皇を自然に「人間として」扱っていることに感心する。 治一郎は、天皇に対しては、「天ちゃん、天ちゃん」とむしろ親しみを持って語り、「天皇もかわいそうだ」といっていたという。天皇は伊勢神宮の神官になったらいい、というのが治一郎の天皇処遇案だと聞いた。たしかに、人間としてはそっちのほうが幸せだろう。 このような「役割として」と「人格として」の区別、それが視点にあったからこそ、父や神様の役割をまことに人問的に果たせたのではなかったか。 |
| もう一つ、「序章としての終章」の中から、私の問題意識と重なる部分を一つ、 『普遍的原理をみずから唱えたときには、負ける』というところを別ページで引用する。  |

